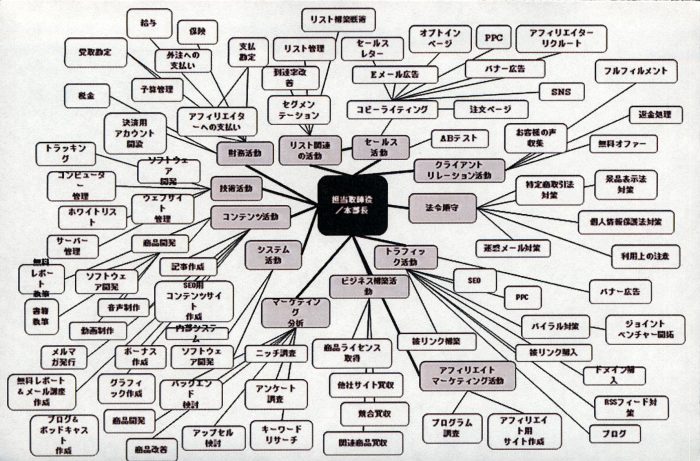本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。
詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2009年2月号(1月25日発売号) に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」四の巻(第4回)「破綻した売掛先の対応」をご覧ください。
当方:
脇甘(ワキアマ)商事株式会社 社長 脇甘 満寿留(わきあま みする)
同社法務部 部長 執高 鰤男(しったか ぶりお)
相手方:
サブ・イクセレント物産株式会社(「サブイ物産」)
破綻した売掛先の対応:
売掛先であるサブイ物産が破綻しました。
当社は、商品引揚げに赴いた際、納入品の見合い分回収として倉庫内の別の商品もついでに頂戴してきたところ、サブイ物産側弁護士から
「先般の商品回収行為は窃盗ないし恐喝に該当する犯罪行為だ。
即刻商品を返還せよ。
しからずんば、刑事告訴する」
と、内容証明郵便による通知書が送られてきました。
当社社長は、商品を取り戻すのは真っ当な自衛行為で、債権者として当然の行動をしたまでだ、と考えています。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:取引先の破綻
たとえ所有者や権利者による搬出や回収であっても、商品を保管管理している債務者に無断で持ち出したら、即、窃盗罪が成立します。
搬出の際に脅迫したり暴力を振るったりした場合、恐喝罪や強盗罪が成立することすらあります。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:商品引揚げ財産搬出行為に関する裁判例
裁判商品引揚げ行為や財産搬出行為の違法性が問題になった裁判例があります。
破産申立直前の会社の倉庫から債務者(後日、破産)の承諾なく印刷機等を搬出したことを問われた債権者は、
「債務者との間の機械売渡証書を所持しており、機械搬出行為はこの証書に基づくものだ」
と弁解しましたが、裁判所は、当該証書を偽造と断定し、その結果、搬出に関与した債権者及び機械を買い取った者の行為を共同不法行為として、彼らに損害賠償を命じました(東京地裁平成13年7月10日)。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点3:商品引揚げ行為や財産搬出行為についての債務者の了解
商品引揚げや財産搬出行為については、債務者の了解さえあれば違法性はなく、民事上も刑事上も一切問題にならない、ということにはなりません。
法律実務においては、当該了解の程度や了解を得るまでの経緯についてその合理性が厳しく問われ、また、了解を得たとしても搬出行為の方法についても厳しくチェックされることもあります。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点4:売掛先破綻対策
中小企業に掛で商品を卸す行為は
「いつつぶれるかわからない会社に無担保で融資する行為」
と同じであり、そのようなリスキーな貸付をするのであれば、合理的担保を徴求するか、焦げついても影響がない程度の掛に留めるべきなのです。
破綻先に買掛やその他債務がある場合、自社納入商品代金債権で相殺すれば、事実上焦げついた債権が回収されたことになります。
このように、取引破綻時に唯一有効な債権回収手段といえるのは相殺のみであり、まずは相殺の可能性こそ検討されるべきです。
助言のポイント
1.たとえ債権者でも、債務者に無断で債務者保管の商品や財産を持ち出すことは、自力救済禁止の原則により、違法とされる。
2.無断の財産搬出行為は、窃盗罪のほか強盗罪(暴力や脅迫を行った場合)に問われる場合もあるので、絶対しない。
3.債務者の搬出許可を取得する場合、慎重に取り付けておかないと後日無効と言われる可能性もある。
4.「正当な権利があるのであれば、正当な法の手続きを踏んで債権回収をはかればよい」というのが裁判所のスタンス。破綻先からの債権回収は拙速よりも巧緻に行う。
5.何時つぶれてもおかしくない中小企業に掛で商品を卸すのは、不良な債務者への無担保融資と同じで非常に危険。相殺を含めた合理的担保の徴求をした上で、適切な与信管理を行う こと。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:
企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所