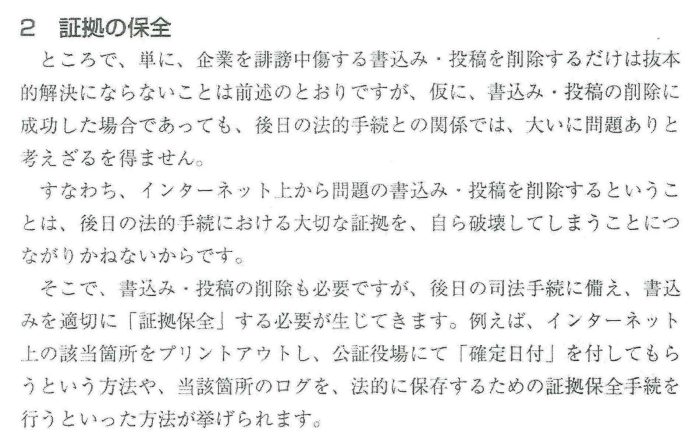かかりつけ医をもつようなイメージです。
今後、法律相談ないし各種ビジネスや社会経済生活上の課題や不安が生じた場合に、問題解決に至るまでの時間とコストが節約でき、また、いざというときには、課題対処を支援してくれる用心棒がいてくれる安心感を提供するものです。
顧問契約の有無による対応の差を説明すると、よりわかりやすいでしょうか。
1 顧問契約がない場合
・各種ビジネスや社会経済生活上発生する、「明確な事件や事案や課題や相談事」に至らない、単なる不安やストレスや違和感の段階では、なかなか気軽に相談することが困難
・かつ、相談が遅れた場合、解決が困難になる場合が生じる
・相談実施までにアポイントや申込みが必要で、また、弁護士は顧問先を優先するので、アポイントが入らない場合がある
・カルテに相当するものが整備されていないので、自身の状況を逐一説明しなければならないので、無駄な時間が生じる
・相談の中で、弁護士が関与すべき事案であっても、医師のように応召義務がないため、弁護士は、多忙や、割に合わないなどを理由に、事案受任を拒否する自由をもつ
・事件終了した場合、通常、事件終了後しばらくは不安定な状況が続くが、事件が終了後は、接点や関係がなくなるため、弁護士としてはケアしない。特に、再発防止や同種リスク、さらには、派生事件については、弁護士として対応する義務や責任を負わない
2 顧問契約がある場合
・単なる事業や生活設計を含め、各種ビジネスや社会経済生活における現況や将来的な方向性を共有しておける
・各種ビジネスや社会経済生活上発生する、「明確な事件や事案や課題や相談事」に至らない、単なる不安やストレスや違和感の段階でも気軽に相談できる
・異変や事件に至らない、不安や違和感段階で、すぐに相談に対応しているので、着手が早く、先手を打て、結果、解決のスピードと期待成果が改善できる
・カルテに相当するもの(顧問先ファイル)を整備しており、アップデート情報は別として、自身の状況を毎回逐一説明する必要がなく、相談開始の初速が圧倒的に早くなる
・医師のように応召義務がないことには変わりないが、弁護士としては、日常構築された信頼関係に応えるため、顧客継続価値を維持・改善するため、多忙であっても、あるいは、割に合わない事案であっても、受任し、あるいは、受任困難でも、極力最善解を模索する努力を行う
・事件受任の際にも、顧問料に応じて、通常費用から減額プランを提示される
・事件終了した場合、通常、事件終了後しばらくは不安定な状況が続くが、事件が終了後も、顧問契約に基づき、弁護士にケアを求められる。特に、再発防止や同種リスクの相談が可能となり、派生事件についても、相談対応・受任対応を求められる
なお、特定事件の受任に伴う、キックオフフィー、リテーナーフィー(事件管理料)、成功報酬金は、顧問費用とは別になります。
最後に、プライバシーの問題について、懸念する方もいるようですが、弁護士には、法律上の守秘義務があり、秘密漏洩は処罰対象あるいは業務上の懲戒処分の対象となります。
もとより、この職業についたときから、秘密は墓の中まで持っていくことは職業倫理として堅持しています。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:
企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所