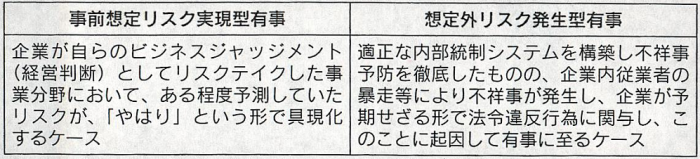民事訴訟法改正を契機として、民事訴訟実務が大きく変化し、法改正後約四半世紀を迎え、このような変化もすでに実務運用として定着してきました。
企業の民商事争訟法務(契約事故・企業間紛争対応法務)に関しても、当然このような変化に対応することが求められます。
民事訴訟法改正による実務の大幅な変化という点もふまえ、企業として契約事故・企業間紛争に起因した民商事訴訟に関わる場合における訴訟対応の実践的なポイントを述べていきます。
訴訟弁護士といっても、民商事訴訟法改正により大幅な権限を付与された裁判所からみれば、
「裁判所というお役所に出入りし、『入札受注』ならぬ、『判決』という結果を欲する外部の業者」
と同じです。
「出入りの業者“風情”」
が納期を遅らせたら出入禁止になってしまうのと同様、弁護士にとって裁判所が指定した主張書面や証拠提出の納期厳守は絶対です。
訴訟を遂行する上では、様々な課題(言い分の整理や言い分の裏付けとなる証拠)の提出が要求され、その全てについて納期が設定されます。
例えば、
「いついつまでに、この点を調べてこい、この点について主張内容を整理しろ、こういう証拠があれば出せ」
という具合に裁判所から要請されます。
また、法廷や弁論準備室でのやりとりは時間が限られていますので、期日での時間を効率的に使うためには、議論の素材である主張や証拠は事前に提出しておくべき必要があります。
この観点から、課題提出期限は、弁論期日等出頭日の1週間前等の前倒しで設定されますが、無論これも納期厳守が求められますし、仮に納期が維持できないようであれば、いわゆる報連相(報告・連絡・相談)を行い、事前に対応を協議しておく必要があります。
訴訟遂行上、納期厳守や遅れた場合のフォローなどは、単純なことですが、少しでも裁判官の心証をこちらに有利に運ぶためには重要です。
民事訴訟法改正前から活動されている弁護士の中には、この種の期限遵守にルーズな人もいますが、基本的にこういう弁護士は裁判官に嫌われます。
そして、
「期限も含め、約束というものは、全て厳守すべし」
という生来的気質を有する裁判官が当事者の生殺与奪を握っていることも考えれば、裁判官に嫌われることは訴訟対応戦略としては推奨できません。
この点は、控訴審における控訴理由書提出期限についても同様です。
ルーズな弁護士の中には、
「控訴理由書提出期限は一種のガイドラインに過ぎないから、控訴理由書提出期限に遅れたからといって却下はされない」
などとうそぶき、平然と控訴理由書提出期限に遅れて提出する方もいらっしゃいます。
しかし、前述のとおり、
「時間にルーズな弁護士が裁判官から嫌われる」
という前提は、
「書かれざるルール」
としてきっちりと把握しておくべきことは当然です。
そもそも、裁判官という人種は、どんな人種でしょうか?
もう少し詳細に分析してみます。
「裁判官(書記官を経由した簡裁判事を除く)」
という属性をもつ集団は、中央省庁のキャリア組と肩を並べるほど、東大法学部卒占有割合が高く、しかも、その圧倒的大多数を占める東大法学部卒の裁判官は、官僚と違って、司法試験に20代前半くらいに合格しており、かつ、司法研修所の成績も相応の好成績を修めている、という方々です。
おそらくそういう方々は、小学生から以来ずっと、宿題なり課題なりレポートなり、およそ提出期限とか納期とか言われるものは、すべからく期限遵守してきて、それが人生の基本と考えているようなタイプの人種です。
そうでないと、東大に合格したり、司法試験を若い時分に、高い成績順位で合格したりできませんし、研修所も好成績を取れませんし、裁判官になりたくても、任用当局(最高裁事務総局)からお声がかかりません。
憚りながら、筆者自身が、そういう経歴スペックに近似した経歴を持ってしまっているので、裁判官の思考や感受性は、
「(是非は別として、)理解できるか理解できないか」
と言われれば、よく理解できてしまいます(なお、理解はしていても、弁護士稼業をしている関係で、周囲にそれを期待するほど幼稚ではありません。在野の弁護士を四半世紀もしていると、
「世の中のほぼすべてがいい加減でだらしない方々である」という現実を認識できる程度には世情に通じています)。
とはいえ、弁護士といっても、いろいろな方がいらっしゃり、
「東大に合格できず、司法試験に合格はするものの、『若い時分に、高い成績順位で合格』することが叶わず苦節○年でようやく合格し、司法研修所でも好成績を取れず、裁判官になりたくても、そのはるか以前の段階で、任用当局からお声がけされる対象から外れてしまっており」
という形で、弁護士以外の選択肢が事実上存在しない状況で、当然の進路として弁護士となったような方もいます(「『東大に合格し、司法試験を若い時分に、高い成績順位で合格し、研修所も好成績を修め、裁判官に任官しないか、と任用当局からお声がかかる』というタイプの法曹」が優れていて、「そういうプロファイルを持っていない法曹」がダメだ、と言っているわけではありません。単純に、「弁護士という属性をもつ集団ないし組織の中も、細かに観察すれば、様々な経歴上の偏差が有意かつ顕著に存在する」という事実ないし現実を指摘しているだけであり、他意はまったくございません)。
弁護士の中にも、
「『東大に合格し、司法試験を若い時分に、高い成績順位で合格し、研修所も好成績を修め、裁判官に任官しないか、と任用当局からお声がかかる』というタイプの(裁判官の経歴ないしバックグラウンドと近似する経歴等を有する)弁護士」
もいるのでしょうが、他方で、そういう
「裁判官の経歴等とは“真逆”の経歴等」
を有する弁護士の方々もおります。
そして、後者の中には、(すべてとは言いませんが)
「およそ提出期限とか納期とかいわれるものは、すべからく期限遵守してきて、それが人生の基本」
という裁判官の思考や感受性が全く理解できない方々もいらっしゃるかもしれません(裁判官の思考や感受性が理解できても「それがどうした。そんなの関係ねえ」とうそぶく弁護士の方もいるでしょう。思考や感受性が理解出来て対応の必要性・有用性が理解できても、生来のだらしなさが災いして、対応が困難、という弁護士の方もいらっしゃるのかもしれません。実際、控訴期限徒過で少なくない数の弁護士が懲戒処分を受けている事例を目にしますと、改めてこのような分析の正しさを実感します)。
しかしながら、
「小学生から以来ずっと、宿題なり課題なりレポートなり、およそ提出期限とか納期とかいわれるものは、すべからく期限遵守してきて、それが人生の基本と考えている」
ような裁判官がもつ基本的・原則的な思考や感受性を基本とすると、
「『時間を守らない、守れない、ルーズな人間』は、ゴミや汚物と同じように認識、評価される」
ということになると思われます。
このことは、是非は別として、立場を交換して、想像すれば容易に理解されるところです。
「裁判官の感受性を想像しながら、裁判官の目線で『弁護士という属性集団』を観察した場合に内面に投影される心証の風景ないし状況」
を描写すると、(裁判官の目からみれば)経歴上の偏差が有意かつ顕著に存在しており、よく言えば
「多士済々」
もっと率直に表現すると
「スペックは様々で、『その中には、同じ法律家とは認めたくないような、極度にいい加減な連中も相応にいる蓋然性』もある、玉石混交の集団」
ということになるのかもしれません。
そのような認識前提からすれば、
「裁判官目線での観察・評価として、納期や期限を守れないような弁護士を、ゴミや汚物のように嫌悪する」
という事態の発生も、蓋然性としては大いにあり得るものと考えられます。
もちろん、
「納期や期限を守れないような弁護士を、ゴミや汚物のように嫌悪する」
という顕著な嫌悪感・忌避感が生じても、
「天皇陛下と同様、普通は感情や心証を表さない、ポーカーフェースの裁判官」
としては、そのような感想や印象を口に出して、ストレートに、情緒豊かに表現するようなことはなさいません。
そんなことをしても
「納期や期限を守れないような、(裁判官の心象風景として)ゴミや汚物なみに嫌悪しているだらしない弁護士」
が改心して態度を改めるとは想定しがたいですし、第一、そんなことをしても無駄で無意味であり、無用かつ不用意に敵を作るだけです。
ただ、口に出さないからといって、
「納期や期限や約束を守らず、忌避感や嫌悪感を生じた」
という事実がなくなったわけではなく、しっかりと心証に影響し、しっかりと後で報復されることはあり得ます。
要するに、
「そんなだらしない弁護士の言っていることがまともな主張である、という経験上の蓋然性は絶無である」
という考えの下、当該(だらしない)弁護士に不利な心証を形成して、
「当該経験則を前提とした思考経済・訴訟経済に即した心証形成(別名:予断と偏見)」
を前提に、当該弁護士に対して、後で、報復よろしく敗訴判決を食らわして、忌避感情や嫌悪感を清算すればいいだけですから。
そもそも裁判官は、
「江戸の敵をスマートかつエレガントに長崎で討ち、後は知らんぷり」
ということをやってのける
「(当該事件に限って、という限定はつくものの)中世封建国家の専制君主並の絶対権力」
をもっており、小言や苦言をちくちくいわずとも、ポーカーフェースでやり過ごし、あとでじっくりとその権力を適正に行使して、目にもの見せてカウンターを食らわせれば、いいだけなのです。
ただ、
「天皇陛下と同様、普通は感情や心証を表さない、ポーカーフェースの裁判官」
も、ときには、この
「納期や期限や約束を守らず、忌避感や嫌悪感を生じた」
ことを口に出して、苦言を呈することがあります。
私個人としては、理解できます。
そりゃ、裁判官も人間ですから、あまりにもだらしなくていい加減な人間のどうしょうもない行為をみたら、小言や苦言が口をついて出る、ということもあるでしょう。
引用開始==================>
橋下さん、多忙はわかるが…裁判長苦言
事件発言控訴審
山口県光市の母子殺害事件の被告弁護団への懲戒請求をテレビ番組で呼びかけた橋下徹弁護士(現大阪府知事)が、被告弁護人を務めた弁護士4人へ1人当たり200万円の支払いを命じられた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が16日、広島高裁(広田聡裁判長)であった。
広田裁判長は、橋下氏側が控訴理由書の提出期限を過ぎたうえにこの日までに3通に分けて提出し、さらに4通目があると予告したことについて、「多忙なのはわかるが、(橋下氏は)代理人を立てているのだから提出は可能だったはずだ」と苦言を呈した。
民事訴訟規則で控訴理由書の提出期限は控訴から50日以内と定められている。
橋下氏の本来の期限は昨年11月27日だったが、橋下氏側は12月12日までの延長を申請し、1通目を同日提出。2通目は今年1月6日、3通目は第1回口頭弁論のこの日に出した。
(朝日新聞DIGITAL 2009年2月16日22時7分配信)より
<==================引用終了
上記事件ですが、予想通りの展開として、橋下側は、(控訴理由書提出期限に遅れ、苦言を呈された)控訴審で敗訴しました。
他方、橋下氏は、この事件を最高裁に上告し、最高裁では逆転勝訴しています。
「結果として勝ったからいいじゃないか」
というのは、後知恵によるあまりに単純で幼稚な見方です。
高裁で、もっと真面目にやっていたら、高裁段階でも勝訴した可能性は高く(最高裁でひっくり返るような要素が内在してわけですから)、何も
「土壇場も土壇場の、最高裁に至ってようやく大逆転劇」
という、
「(勝率が数%以下の)危なっかしい勝ち方」
をせずとも、もっと安心して勝ちが取れた筋の事件で、無駄に星を落とした、という見方もできます。
高裁では、あまりのデタラメさや、ルーズさに激怒して(「天皇陛下と同様、普通は感情や心証を表さない裁判官」がわざわざ口に出して苦言を呈するのはよほどのことです)、事件の筋より、とにかく、嫌悪感や忌避感が先立って、報復の敗訴を食らわされた、という観察・評価も可能です。
とにかく、時機に遅れず、納期を守る、というのは、重要です。
また、最悪、納期を守れない場合も、そのような原因や背景を切々と訴え、いつになったらその納期遅延の原因が解消し、約束が果たせるか、現実的なリカバリー計画を策定して、弁解し、理解を得て、許しを請うような、謙虚、もっといえば卑屈に見えるくらい、可愛げな態度をみせるべきです。
特に、控訴審における控訴人側は、一審での負けを取り返す、チャレンジャーの立場ですから、控訴理由書提出期限の厳守は、絶対維持すべき基本的スタンスといえます。
運営管理コード:CLBP115TO116
運営管理カテゴリー:有事対応フェーズ>法務活動・フェーズ4>民商事争訟法務(フェーズ4A)>(4)対応のポイント>納期厳守
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:
企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所