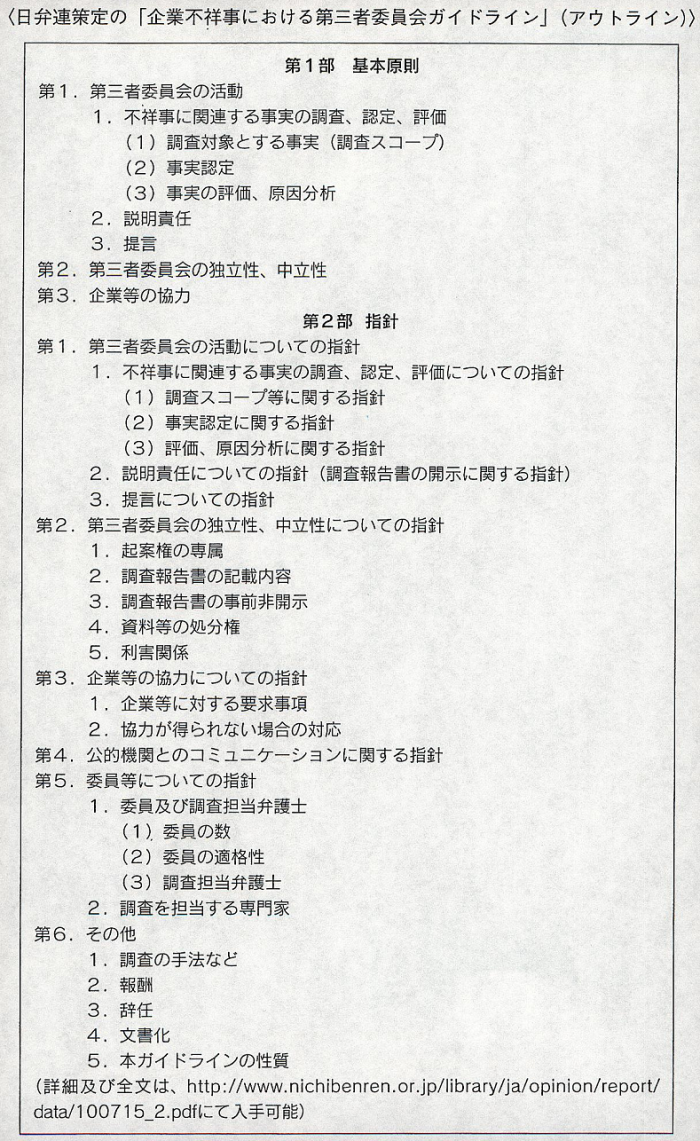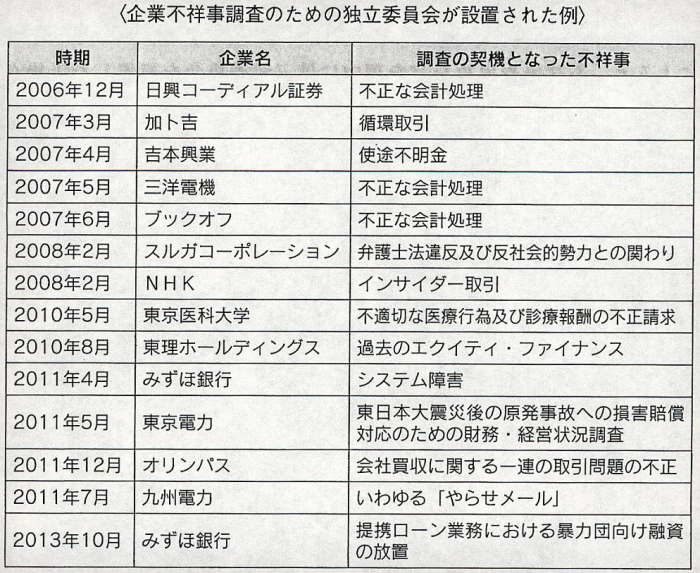法務活動の中で、現代型企業法務の中核である予防法務、すなわち、 トラブル予防のための法務活動が挙げられます。
予防法務は、契約事故・企業間紛争を防ぐための予防活動(契約法務)と、法令違反を防ぐための予防活動(コンプライアンス法務)とに分類されます。
前者に関しては、契約自由の原則に立脚し、企業の優位を確立するため、提案された契約書のリスク・シミュレーションとリスク・コントロール(リスクの回避・移転・保有等)を行い(契約書精査)、契約条件について利己的・功利的に交渉し(交渉法務)、その成果を緻密に文書化していくこと(契約書作成法務)が活動のポイントとなります。
ここで、契約書作成やレビュー、校正する、という企業法務活動を行う上で、重要な前提知識を確認しておきます。
まず、
「契約書に何を、どのような形で記載するか」
ということについては、公式なルールは一切ありません。
契約書というのは、紛争予防のための重要なツール・デバイスと認識されておりますが、具体的な訴訟の場面での機能・役割としては、
「証拠」
の1つ(とはいっても重要な証拠ですが)に過ぎません。
すなわち、契約書は、
「一定の時点において、当事者間において、一定の合意がなされた」
という事実が記録されたものであり、合意内容に関して紛議が生じた場合に、議論のスタートとして、共通認識としての合意内容を確認する際に、合意内容を記述したもっとも端的かつ確実な記録としての契約書が、証拠として使われることになります。
どのような内容を書くかは当事者間の自由であり、公序良俗に反するものでない限り、どのような約束を書いても自由であり、約束が理解可能で具体性がある限り、書いたら書いた分だけ、法的効果が認められます。
書き方も、書く順番も、文体も、字体も自由です。
「甲」「乙」
という略称を使わなくても結構です。
「A」「B」「C」
でも
「α」「γ」「β」
でも、あるいは、
「トヨタ自動車株式会社、以下、『TMC』という」
という形で、適当な略称ないし記号を用いても構いません。
常体、敬体、方言でも構いませんし、字体も、明朝でもゴシックでも行書体でもギャル文字でも構いません。
内容も平均的裁判官が了解可能な程度に具体性と明確性があれば大丈夫です。
「利益を均等に配分する」
という内容も、
「利益は折半」「半々」「山分け」「プロラタ」「頭割り」
いずれでも意味は通じると思いますので、絶対駄目というわけではありません(裁判官に気持ちよく、ノイズを感じずに読んでもらう、という意味においては、表現上の選択としてはよく考えるべきですが)。
使用する紙も、コピー紙でも、ダンボール紙でも、ハンカチでも、紙ナプキンでも、板でも、構いません。
新聞紙やチラシに書いてもいいのですが、判読できない場合のリスクを考えると、おすすめできませんが、
「新聞紙やチラシに書いたら即無効」
と断言するような法律があるわけではありません。
思考を柔軟にして本質をご理解いただくために、極論を申し上げましたが、あまり奇天烈な契約書を用いた場合、裁判所がドン引きして、証拠の価値を低下させたりするかもしれません。
数百億円のM&Aの契約書が、紙ナプキンの上に、鉛筆で、河内弁を用いて、ギャル文字で書かれてあった場合、裁判所が、合意の真摯性を疑い、心裡留保と認定し、契約の瑕疵を認めるかもしれませんが、そのあたりは、自由心証主義に委ねられます。
紛争予防効果の高い、いざというときに役に立つ、良い契約書というのは、取引内容が具体的かつ明瞭に記述され、かつ、将来の不愉快な出来事が生じた場合の両当事者の対処方法が明確に定められているものです。
その意味では、まず、取引内容が曖昧で抽象的であってはならず、具体化、明瞭化されていることが先決課題として重要です。
この点、依頼部署である営業部門や企画部署では、曖昧で適当な合意内容で、あとは、
「実際やってみて、様子をみながら、もし問題があったら、あとは円満に話し合いで」
というスタンスで取引を走らせ、相当な資源動員を開始することを目論むかもしれませんが、このような内容を契約書として文書化したところで、紛争予防効果は皆無であり、たとえ、契約書があっても、トラブルに発展する危険が大きいことは明らかです。
したがって、法務部としては、契約書を作成する前提として、まず、取引内容を具体化、客観化、明確化する方向で、依頼部署に、条件を詰めさせることを指導することになります。
また、契約内容が狂った内容である場合、どれほど緻密な契約書があっても、紛争が防げません。
例えば、
「遠方の発展途上国にある、全く信用実績のない会社との間で、数億円の商品を掛売りし、契約トラブルは、先方の裁判所で解決する」
という、経済合理性も取引安全性も皆無の、ビジネス的には狂っているとしか言いようがない取引内容を、どんなに緻密に文書化し、大部の契約書を作り上げたところで、債権が支払われなければ、即座に、ギブアップするほかありません。
これは、契約書の問題というより、取引設計の問題であり、取引内容が、経済合理性や取引安全性の点で常軌を逸した内容であれば、どんなに優秀な弁護士が、どんなに立派な言語と文書で、分厚い契約書を作ったところで、
「狂った取引内容を正確に記述した」
というだけであり、紛争予防効果など期待すべくもありません。
最後に、契約内容は簡素でも、緻密でも差し支えありませんが、
「書いていないことは、何をやっても自由」
というのが、取引法の大原則です。
「何をやっても自由」
というのは、法律に反しない限り、どんなに不正義で不公平で非常識で卑怯で姑息で容認しがたいものであっても、
「やりたい放題」
ということを意味します。
もちろん、民法に定めのある典型契約に該当する場合、民法所定のルールが適用されますし、また、あまりに不正義な行為については、権利濫用や信義則といった一般法理で救済されることもあるにはありますが、基本的には、
「書いていないことは、何をやっても自由」
であり、
「やられたくなかったら、やられて困ることを発見・特定し、言語化・文書化して、禁忌事項とペナルティを記述しておく」
ということが推奨されます。
運営管理コード:CLBP23TO24
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:
企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所