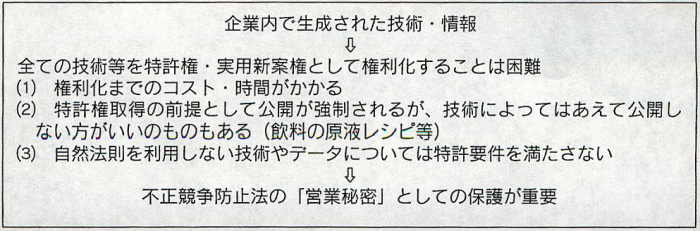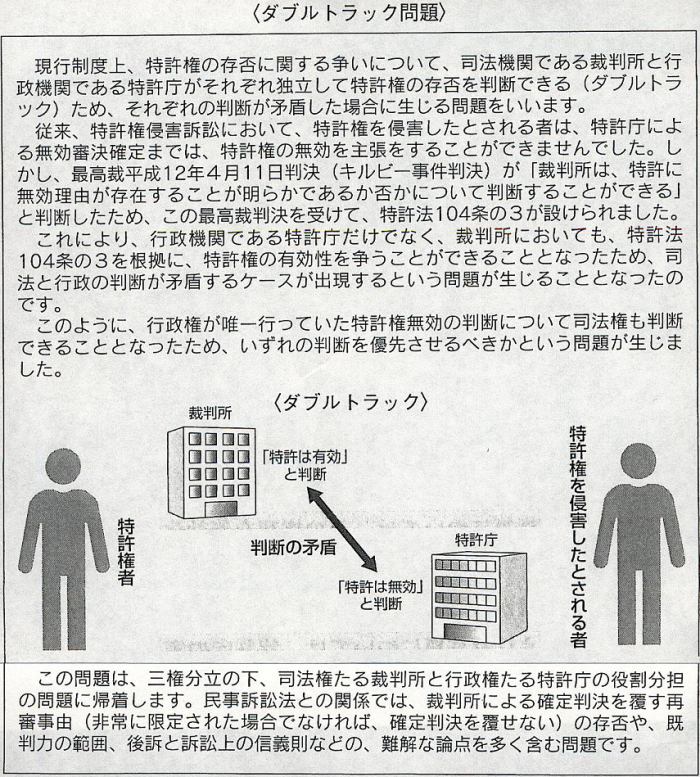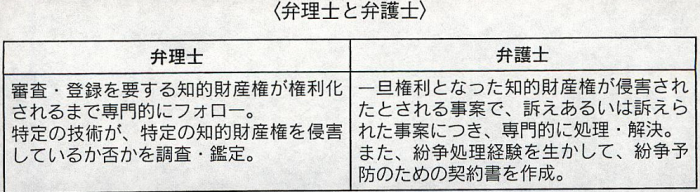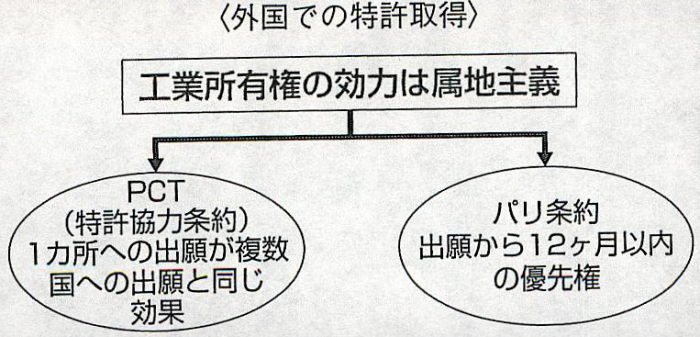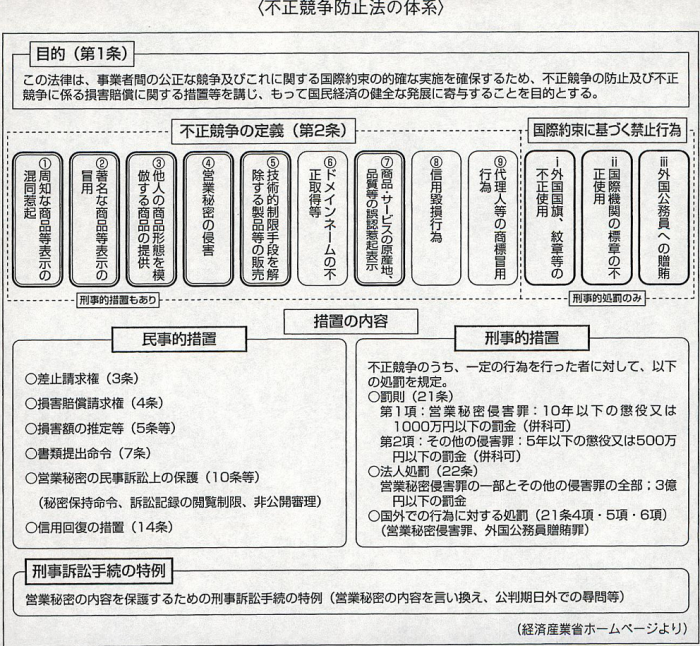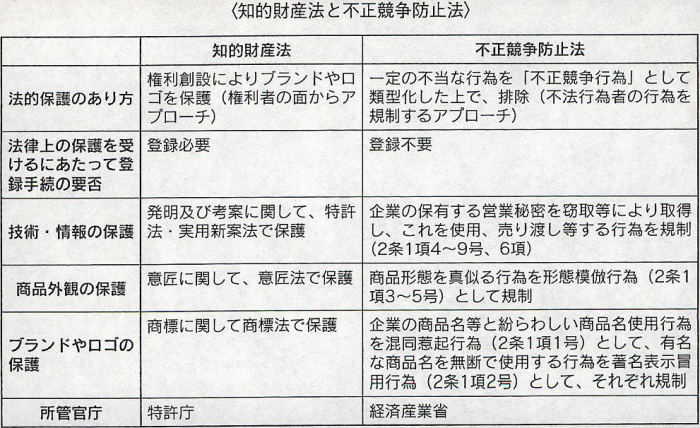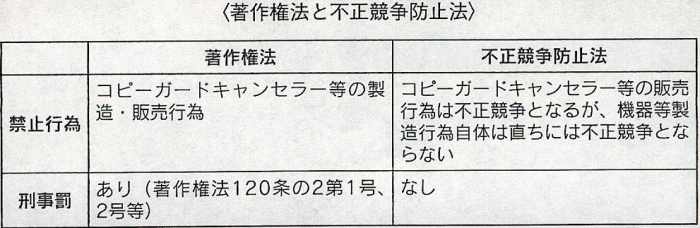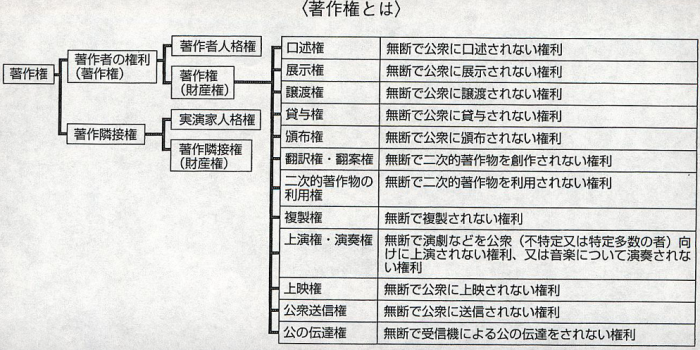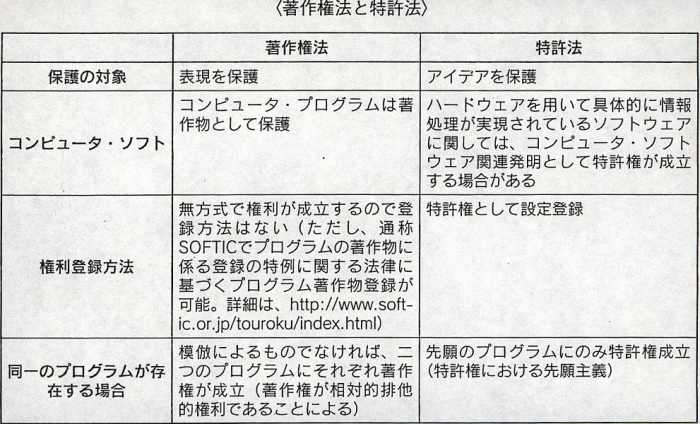かつて、特許訴訟においては、訴訟の前提となるべき課題である
「侵害行為の特定」
という点に関し、長期間にわたって激しく争われるのが通例でした。
すなわち、特許訴訟を進める上では、
「原告の有する特許」
と
「侵害品(知財訴訟においては“イ号物件”と呼称されます)あるいは侵害方法(“イ号方法”)」
とを比較してどの部分がどの程度似ているか、という一種の
「間違い探し」
のようなことから始めなければなりません。
しかしながら、被告側は、訴訟戦略上、この
「間違い探し」
プロセスに協力しない姿勢を取る方が有利であると判断し、イ号物件やイ号方法を提出しない、あるいは、提出したとしても当該侵害品ないし侵害方法の機序・作用の詳細を明らかにしない、という形で抵抗します。
このようなことから、
「間違い探し」
ゲームの対照図がなかなか出てこず、明らかになるまで訴訟が相当程度事実上停滞する、という状況が生じたのです。
侵害行為の立証を容易にするため、特許法104条の2が設けられました。
これは、
「被告が原告主張のイ号目録を否認する場合には自己の具体的態様を明らかにしなければならない」
という規定です。
相手方が支配する環境において、どのような特許権侵害がなされているのかということを、原告が摘示することは往々にして困難であることもあり、このような定めが設けられました。
しかしながら、この規定を不当に利用することで、相手方の技術を探索しようという戦略法務が実施されることもある、との報告があります。
例えば
「物を生産する方法の発明」(製造方法の特許)
においては、成果物だけを見ても、どのような製造方法の特許を実施することで出来上がったかは通常把握できません。
そのようなときに、ライバル会社が秘匿する特殊な製造方法についての詳細な技術内容を合法的に取得したいと考える企業は、当該ライバル会社に
「この製品は当社の製造方法特許を侵害しているに違いない」
との訴訟を提起します。
これに対し、ライバル会社は、
「そうではない。われわれはAとBという方法を用いて製造したのである」
などと具体的に否認する立場に陥ります。
このように、ライバル会社に反論の具体的理由を開示させることを通じて、ライバル会社の技術の内容が探索できてしまうというわけです。
特許訴訟は
「訴訟」
である以上、原則として公開法廷でなされなければならず(憲法82条)、したがって、訴訟のやりとりを通じて、営業上・技術上の秘密が公になってしまいます。
そこで、特許法は、このような事態に対処すべく、まず、当該
「秘密」
を訴訟の場に顕出させる前に、訴訟の進行のために必要かどうかをインカメラ(特許法は、「正当な理由」がある場合を除き、侵害行為等の立証のために証拠の提出を命じることができることを定めています。そこで、この「正当な理由」の存否を判断するために、裁判所のみが証拠を閲覧する手続をインカメラ審理といいます)にて審理を行うことができると定めています。
また、仮に必要であるという判断に至ったとしても、訴訟追行のため以外に当該情報を用いてはならないことなどを内容とする
「秘密保持命令」制度
を整備しています。
技術探索目的での訴訟を受けた相手側としては、これらの措置を申立てることにより、訴訟手続の進行を妨げることなく、しかも、それを開示したことで訴訟上も経済上も不利益を被らないように手当てがなされているのです。
そして、その実効性を担保するため、秘密保持命令に違反した場合には5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれらが併科され、法人も罰せられることがあります(特許法200条の2)。
したがって、技術情報等に関する訴訟の当事者となった場合には、秘密保持命令の申立てや、非公開審理の利用を行い、ノウハウの不当な開示・流出から企業を防衛することになります。
運営管理コード:CLBP355TO357
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:
企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所