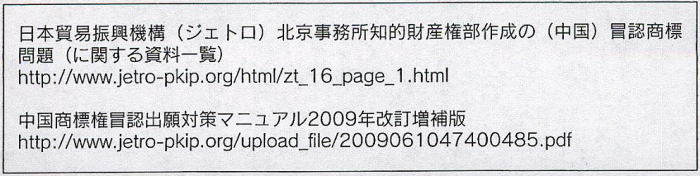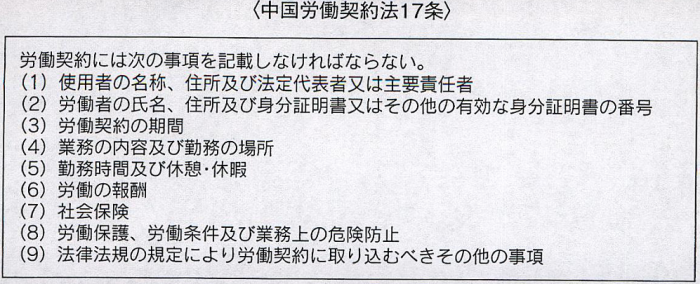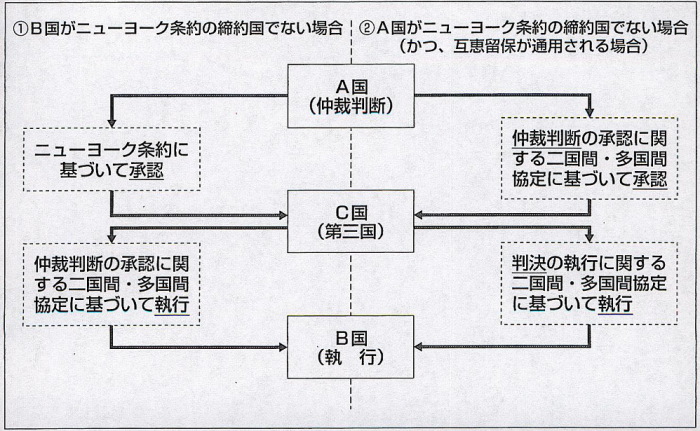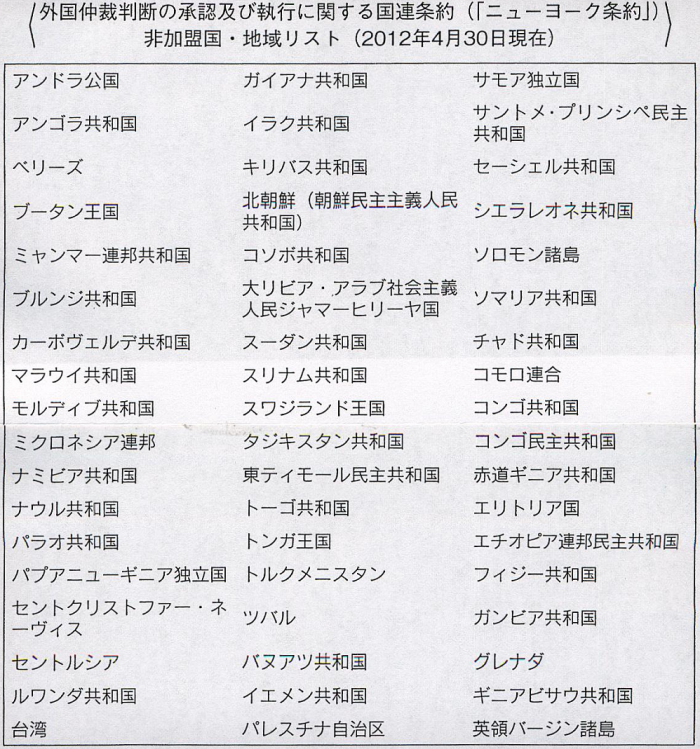民事再生と破産をまとめて
「法的整理」
といいます。
「『任意』整理」
と対語になる、という意味で、
「『法的』整理」
という言葉が出てきます。
法的整理は、要するに、裁判所という国家権力を使って、
「借りたものは、約束通り、きっちり返す」
という契約法理を捻じ曲げて、有無を言わせず、債権を大幅カットする、という
「鎌倉時代等の徳政令」
に似た、強権手段を意味します。
特定調停も、裁判所を舞台にし、裁判官が出てきますが、あくまで、仲介役というか、お節介役であり、
「契約に基づき発生し、法的に有効に存在している債権を、債権者に意向を無視してぶっ飛ばす」
という過激かつ強権的な手段は使えません。
特定調停が出来るのは 「債権をカットされればどうでしょうか?」
という提案であり、お節介だけです。
その意味で、特定調停は、任意整理のプレミアム版、という位置づけです。
この、法的整理ですが、大きな括りでいうと、民事再生と自己破産があります。
ざっくり申し上げると、
「民事再生は債権の一部カット(一部チャラ)」
「自己破産は全額カット(全額チャラ)」
という、
「徳政令の過激さの度合いによる区分」
といえます。
法人の場合は破産によって法人格は消滅し文字通り成仏ないしお陀仏となってしまいますが、個人の場合、自己破産でも、再生出来ないわけではありません。
すなわち、個人の場合、自己破産、すなわち、経済的なお葬式を挙げたあと、キリストの復活ではありませんが、復活の儀式がきちんと用意されているるのです。
これは、
「免責」
と言われるもので、破産によって確定した破産債権を、全額チャラにして、これから、再スタートを切ってがんばれ、という再生手続きがきちんと用意されています。
ですので、個人の場合でみれば、民事再生も、自己破産も、いずれも、
「支払いができなくなった債務者を、国家権力が介入して、借金を一部または全部チャラにして、借金の無間地獄から救済する」
という点では趣旨を同じくするものです。
個人の民事再生については、いろいろな特殊パターンが存在します。
例えば、個人の民事再生事件で、5000万円以下の担保がない債権がある場合、原則3年間で返済する
「再生計画案」
を作成して許可されたら、借金がなくなります。
「3000万円のうち2000万円をカットするので、年間330万円を3年間返済して、残りはチャラ」
というイメージです。
また個人の民事再生事件で、再生債務者が
「マイホームを残したい」
という意思が特に強い場合、
「マイホームの清算価格分だけ支払い、残りはチャラにして、助けてよ」
という柔軟な交渉も可能です。
例えば、マンションを5000万円で買ったけれども、ある程度ローンを支払い、今はローン残額が1200万円だったとしましょう。
この場合、
「マンションのローン残1200万円についてはきっちり返すので、家だけは手元に残すことにして。その他のローンは、チャラにして、助けて」
という要望が通る可能性がある、というわけです。
したがって、個人の民事再生事件については、
1 マイホームなど、どうしても残したい生活基盤を別枠にして、借金チャラの交渉をしたい場合、
2 言葉の問題として、「民事再生」という響きであれば我慢できるが、「破産」というおどろおどろしいレッテルを貼られるのはどうしても避けたいというセンチメントをお持ちの場合、
破産ではなく、民事再生が検討されるべきことになります。
逆にいうと、個人の民事再生事件について
「家は賃貸でいいし、車も必要ない。今の生活家財だけで十分」
だし、
「破産だろうが民事再生だろうが、言葉は違うが、まあ、同じようなもんだし、同じように裁判所にお世話になるんだったら、綺麗さっぱり全額チャラにしてもらって、すっきり再スタートを切りたい」
ということであれば、民事再生より、むしろ破産を選ぶことになります。
運営管理コード:YSJGK***TO***
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:
企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所