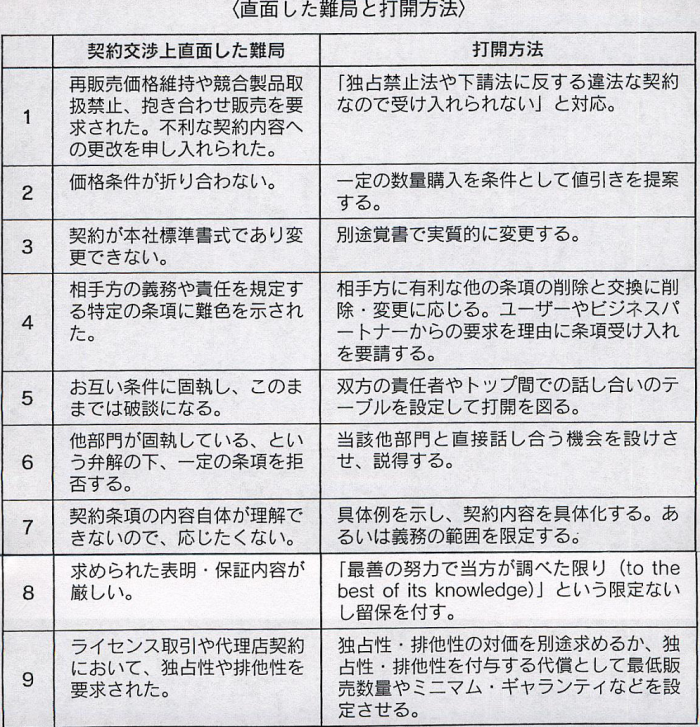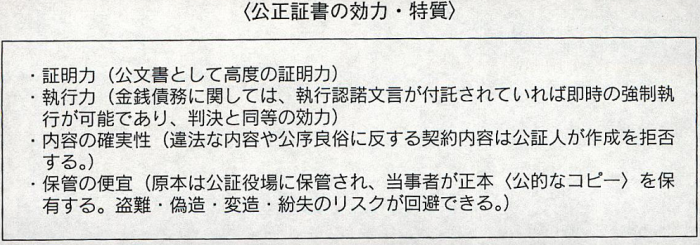内部統制システムとは、
「企業経営を行う上で、絶対根絶不能で、不可避的・恒常的に発生する法令違反リスク」に効果的に対処し、
「大事を小事に、小事を無事に」する
ためのマネジメントプログラムと定義されます。
このシステムを構築・運用するプロジェクトについて、適切に前提環境認識や稼働上の相場観が形成され、リスクや課題も正しく抽出・特定し、認識できた、としましょう。
あとは、さほど困難ではありません。
病気を治すにも、病状と病名が判別しなければ、対処のしようがありません。
他方、病状と病名さえ判別すれば、あとは、それにあった薬を用法用量にしたがって服用するなり、オペを実施して、病巣を取り除けば済む話です。
無論、足が壊死した、手が壊死したといったように、特定の病巣部位が不可逆的なリスクを抱え放置していたら命に関わるということであれば、当該足や手を切り落とすほかありません。
足はそのままにしてほしい、手を失いたくないという気持ちが強くとも、あとは、命を失うか、足や手だけにするか、という選択の問題について、決定すればいいだけです。
リスクについても、同様です。
発見し、特定されたリスクは、回避するか、小さくするか、転嫁するか、原因となっている部分を丸ごと取り除いて処理するか、 です。
「原因となっている部分を丸ごと取り除いて処理する」、
すなわち、不可避的にリスクが伴うような事業であれば、そんな事業などやめてしまえばいいだけです。
「法を犯す前提でないと成り立たない商売」
「法を犯さないと完成しないプロジェクト」
「リスクが巨大で実施してリスクが現実化すると企業をつぶしてしまう事業」
というものも世の中には存在します。
「発覚・露見をしないように商売を続ける」
「いつ発覚するか不安に怯えながらプロジェクトを続行する」
「爆発したら会社が吹き飛ぶという不安を抱えながら事業を始める」
という選択もあれば、そんな商売からさっさと手を引く、というのも1つの見識です。
やめてしまえば、法を犯すリスクや企業を潰すから完全に逃れられます。
いずれにせよ、
「最悪、危なっかしい商売から手を引く」
という究極の選択肢が保障されている以上、リスク管理は
「不治の病で、死ななきゃ治らない」
という類の問題ではありません。
たかが、商売です。
金儲けに過ぎません。
「会社を潰してまでやる必要があるのか」
「法を破って、犯罪者となってまでやる必要があるか」
と冷静になって考えてみればいくらでも選択の余地が出てきます。
東芝は、粉飾決算(チャレンジ決算、不適切会計)をして経営成績を誤魔化す道を選択し、最後に発覚し、企業は存続の危機に陥りました。
さらに、その後、東芝は、傘下のウェスティングハウスが、2015年末に原発の建設会社、米CB&Iストーン・アンド・ウェブスターを買収した際、買収直後に、ある価格契約を締結したことが原因で、7125億円もの損失を原子力事業全体で発生させ、2016年4~12月期の最終赤字は4999億円となり、同年12月末時点で自己資本が1912億円のマイナスという、債務超過の状況に陥りました。
この愚行も、
「巨額の債務負担をさせられ、会社を潰す危険を負担してまで、子会社にこんな契約取引させるべきか」
を、合理的に判断し、いざとなれば、やめてしまえば、塗炭の苦しみを味わうことなどなかったはずです。
東芝は、
リスクに気づかず、
リスクに向き合えず、
リスクをきちんと評価できず、あるいは、
リスクが発現しないと盲信して手を打たず、
「(大きな損失を被っても)最悪、危なっかしい商売から手を引く」という究極の選択肢に気づかなかったか、
気づいていたがサンクコストを忌避して手を引けず、
統制と制御を喪失したことで、企業が危機に陥りました。
いずれにせよ、 内部統制を構築するための哲学や基本理念として、
「法令違反の絶無を目指す、根絶をゴールにする」
などという幼稚で愚劣で非現実的な幻想を目指すものではなく、
「大事が小事に、小事が無事に近づくような」現実的な対処と、
「最悪、危なっかしい商売から手を引く」という究極の選択肢を常に思考前提に置く、
という考え方を忘れなければいい話であり、内部統制の構築・運用は対して難しい話とはいえません。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:
企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所