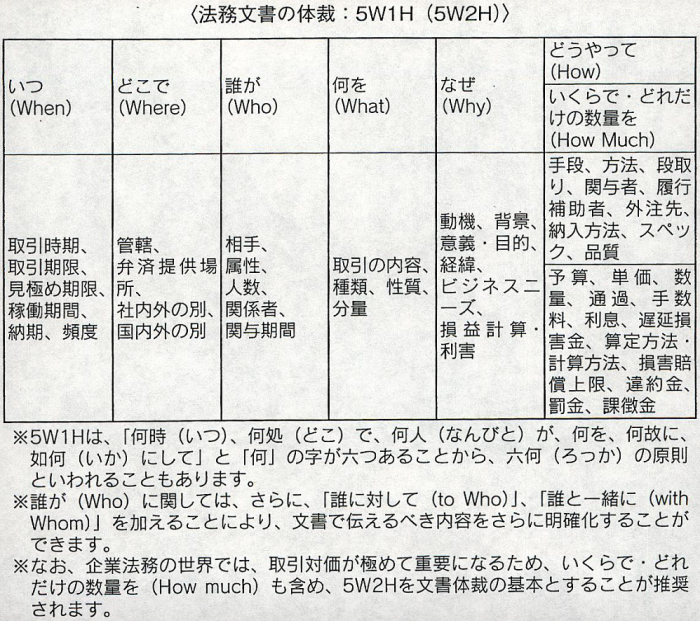法律の無知や無理解は、法的リスクの正しい認識・解釈を阻害します。
企業経営者のほとんどは、法律について絶望的に無知であり、無理解です。
取締役の職責は、読んで字の如しで、
「法令に基づいて、会社の運営を取り締まる専門家」
であり、本当は、法令精通義務というものが観念されるべきなのですが、現行の会社法制度としては、取締役は、試験も資格もなく、誰でもなれます。
それこそ、前科前歴多数の犯罪者であったり、寝たきりで鼻にチューブを差した状態のままのご老人(この状態でも数千万円の役員報酬が支払われることもままあります)でも取締役になれます。
「取締役には、学校も試験も資格もなんにもいらない」
という地位職責の知見レベルがどうなるか、ということは、無試験で合格できる大学の学生のレベルを想像すれば、だいたい予想がつきます。
さらに言えば、法律は、常識では理解できない内容で、日本語でもなく、通常の知識や常識があっても到底読解できないシロモノです。
この点ですでに、法を理解し、法的リスクを把握するのは、容易なことではない、といえます。
ただ、知り、理解するのは容易ではなくとも、興味や好奇心があれば、学ぶことは期待できます。
学校や学校教育が大嫌いで、学校にも行かず、英単語や数式や年号や元素記号等は一切知らない、という不登校で無職の青年も、ホニャララ48のメンバーは、初期メンバーを含め全員フルネームと年齢と誕生日を覚えている、ということもあります。
しかしながら、企業経営者は、法律というものについては、知らないし、理解しないし、知るあるいは理解するハードルが高いし、さらに言えば、興味も関心もなく、むしろ、商売の足を引っ張る憎き邪魔者であり、だからこそ、法を嫌悪し、最低限の理解や興味や関心すら示さないのではないか、と思います。
すなわち、無知や無理解以前に、企業ないし企業経営者としては、法に対する嫌悪感が根底に存在しており、これが企業経営に法的リスクを払拭する営みが進まない原因を構成しているものと思われます。
「法律なんて商売を邪魔するだけの厄介なもの、とっとと消えて無くっちまえばいいのに」
という嫌悪感や忌避感があれば、知ろうとも理解しようともしません、当然ながら、無知や無理解の状態が継続します。
結局、法律のことを理解するのは、事件となって、相応のリスクや実害が生じてから、
「頭で理解する」
のではなく、
「体が痛みとして覚える」
という形で、帰納的に理解が蓄積されていく、というタイプの企業ないし企業経営者も少なくありません。
要するに、他人の注意と警告はすべて無視あるいは軽視し、ストーブの熱さは触って火傷してから理解し、氷の冷たさは握って凍傷になって実感し、包丁の危険性は指を切ってから納得する、というタイプの方です。
そもそも、
「法律は、常識とは無関係に、特に、経済人・企業人のバイアスの塊である『経済常識』『経営常識』『業界常識』と、むしろ対立する形で作られ、遵守を強制される」
という前提が存在します。
商売の常識、健全なビジネス常識に基づく合理的行動の前に立ちはだかり、健全な企業活動(すなわち迅速で効率的で安全な金儲け)を邪魔し、企業の足を引っ張る有害な障害環境、これが企業経営者の法律に対する認識原点(潜在意識のレベルも含めたもの)であろう、と思われます。
その意味では、
「自分の常識なり感覚なりを信じる経営」
「迷ったら、横をみて(同業者の常識と平仄をあわせる)、後ろを振り返る(これまでやってきたことを踏襲すれば大丈夫と楽観バイアスに依拠する)経営」
が一番危ない、ということになります。
以上について、
「経営者は法律を邪魔とは思っていないし、法律をしっかり守っている。何を間違ったことを言っている」
とお叱りの声が聞こえてきそうです。
しかしながら、経営資源、すなわちヒト・モノ・カネ・チエの運用を活動の本質とする企業経営において、もっとも重要なヒトという資源の調達・運用・廃棄に関して規制を行う労働法について、日本の産業社会は、きちんと労働法を知り、理解し、尊重する経営者で満ち満ちているのでしょうか?
この点、 興味深いデータがあります。
各都道府県に労働局が、全国各地に労働基準監督署が設置されており、労働基準関係法令に基づいて事業場に立ち入り、 事業主に対し法令に定める労働時間、安全衛生基準、最低賃金等の法定基準を遵守させるとともに、労働条件の確保・改善に取り 組んでいます。
労働条件の確保・改善を図る具体的な方法としては労働基準監督官が事業場に赴くことなどによる定期監督等(毎月一定の計画 に基づいて実施する監督のほか、一定の重篤な労働災害又は火災・爆発等の事故について、その原因究明及び同種災害の再発防止 等のために行う、いわゆる災害時監督も含む)及び申告監督(労働者等からの申告に基づいて実施する監督)等がありますが、この監督結果が、毎年統計データとして公表されています。
労働基準監督官が行った監督実施状況のデータをみますと、労働違反率は直近でほぼ70%で推移しています。
要するに、ヒトとモノの区別が理解できず、労働法に違反している企業が認知件数ベースで約7割。
認知件数ベースですから、認知にいたらない、お目溢しや暗数等を含めると、体感・実感ベースでは、ほぼ9割近くの企業経営者は、労働法を無視あるいは軽視し、労働法に違反して操業している違法な企業、ということがいえそうです。
こういうデータを踏まえると、
「労働法に興味があり、労働法が大好きで、労働法を進んで理解し知り、労働法を守って、オフホワイトな企業経営をしている立派な企業」
はむしろ稀で、ほとんどの企業は、
「労働法なんて商売を邪魔するだけの厄介なもの、とっとと消えて無くっちまえばいいのに」
という顕在意識や潜在意識をもち、邪魔なことこの上ない労働法を無視あるいは軽視しながら経営しているという実体が看取されます。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:
企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所