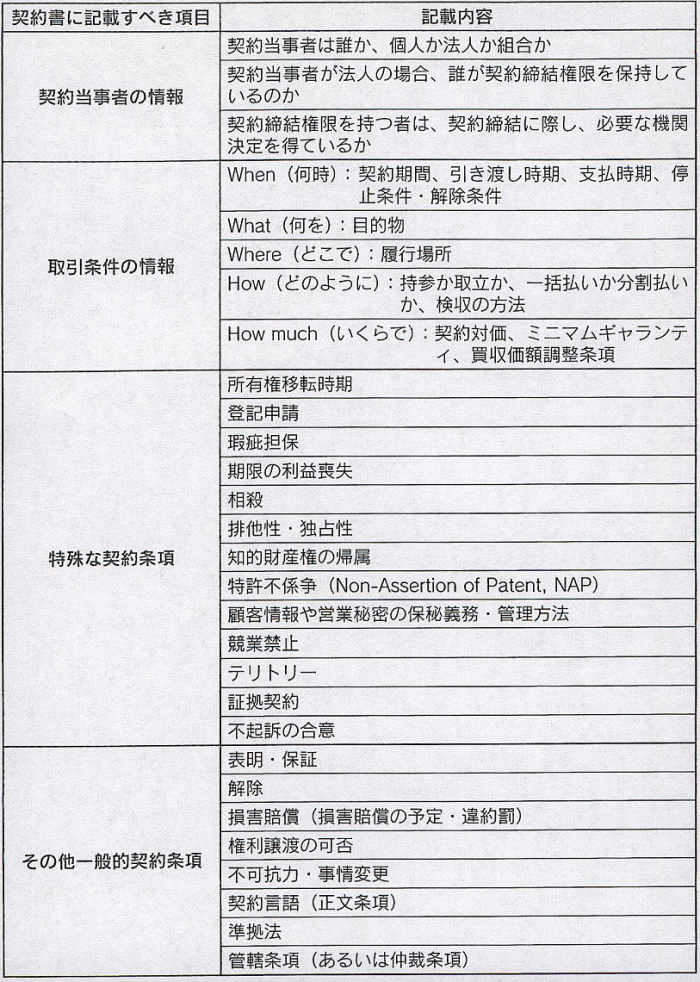法務スタッフが他部門(依頼部門)から契約書のチェックを求められる場合がありますし、また、弁護士も顧問先企業法務部から
「この契約書をチェックしてください」
と要請される場合があります。
この
「契約をチェックしてくれ」
という依頼の趣旨は、一般に以下のような要請と考えられます。
1 代読の要請としての「契約書のチェック」
この場合の
「契約書のチェックをお願いします」
とは、
「契約書に書いてある文書は難解で私の国語力では理解できない。代わりに読んで、何が書いてあるかその概要をかいつまんで一般人でも解る言葉で教えていただきたい」
という要請です。
もう少し具体的に言えば、
担当者としては、先方から提案された契約書が目の前にあるが、自身が機能的非識字状況に陥っており、契約書は日本語で書かれている日本語の文書のようではあるものの、漢字や理解困難な文書や長文が多すぎ、自分には、まるで、象形文字で書かれた知らない国の知らない部族の呪いの文書にしか見えないので、何を書いてあるか、バカな自分でも分かる程度に教えてほしい
という依頼内容です。
実際の
「契約書のチェックの依頼」
のほとんどは、このレベルの依頼です。
営業部が、ある時、
「こんな条項みたことない。これはかなり危険な条項だ。これこれ、エビ、エビ。エビちゃん。エビ担保、エビ担保。エビちゃんの担保とかってやつ。これはかなり高度だよ。ヤバイよ。難しいよ。法務として、しっかりチェックしてよ。」
と大騒ぎして、契約書チェックを依頼しました。
実際は、
「瑕疵担保責任条項」
のことで、
「瑕疵(かし)」
が読めなかったため、
エビちゃんこと「蛯原友里(えびはらゆり)」
の
「蛯」なのか「蝦」なのか
が、字体としてよく似ていたため、大騒ぎした、という話でした。
結局、
「瑕疵担保は、『かしたんぽ』と読みます。瑕疵とは欠陥のことです。購入直後わからなかった初期不良の修理保証を1年分だけ保証サービス提供する、みたいな話で、民法で決まっているものの焼き直し条項で普通のものです」
と回答したら、営業部から
「さすが、法務。やっぱり優秀」
と絶賛された、というオチがついています。
そこそこ大きな企業の話ですが、契約書のチェックのレベル感として納得できる実情をよく表しています。
2 契約書の確認・把握と情報共有を依頼する趣旨としての「契約書のチェック」
この場合の
「契約書のチェックをお願いします」
とは、
「本契約書は、すでに内容を含め社として理解するとともに、特段の校正ないし修正なく締結することが決定しており(あるいは相手方との交渉上の関係や、契約の性質上校正や修正が不可能となっており)、修正やコメントを求めるものではないが、社としてこういう契約を締結することを閲覧し、認識していただきたい。その上で、もし契約上のトラブルになった際には、すみやかに対応いただけるよう事前認識していただきたい」
という要請です。
3 契約書の校正の依頼その1:リスク・アセスメントの要請
この場合の
「契約書のチェックをお願いします」
とは、
「本契約書の意味や内容は理解したが、契約書に書いてある特定の条項の内容が抽象的で、具体的にどのようなリスクがあるのか一見して不明で、あるいは、契約書の特定の条項の解釈・運用の結果、当方が具体的にどのような内容・範囲の義務・責任を負うのか教えていただきたい。なお、リスク・アセスメントいただきたい具体的な箇所は○○条○○項の『○○○』という部分である」
という要請です。
4 契約書の校正の依頼その2: 特定の条項の起案依頼
この場合の
「契約書のチェックをお願いします」
とは、
「 本契約書において、特定の取引条件や特定のリスク予防措置を表現したいが、法的に適切な条項を作成する能力がないので、当該作成を依頼したい。作成を依頼したい具体的な取引条件や特定のリスク予防措置の内容は○○条○○項の『○○○』という部分を『○○○○』という趣旨への変更である」
という要請です。
5 契約書の校正の依頼その2: 契約締結交渉上の助言・対策要請
この場合の
「契約書のチェックをお願いします」
とは、
「この契約書のこの義務や責任は負いかねるので、合理的対案提示や当該条項の削除要請をしたい。その際の交渉ロジックを助言し、あるいは対案の策定及び起案を依頼したい。 作成ないし変更を依頼したい具体的な取引条件や特定のリスク予防措置の内容は○○条○○項の『○○○』という部分を『○○○○』という趣旨への変更である」
という要請です。
6 社外専門家の手配の依頼
この場合の
「契約書のチェックをお願いします」
とは、
「この契約書はリスクが高すぎる、あるいは取引の仕組みが複雑すぎて社内では手に負えないと判断するので、顧問弁護士等の外部法律専門家に、
・契約書作成・校正代理(ドキュメントコントロール)を依頼すべきであると考える、または
・契約交渉代理(ネゴシエーションコントロール)を依頼すべきであると考える
ので、しかるべき外部法律専門家を、予算の範囲内でもっとも費用対効果が高い方法で調達し、目的を達成したいので、
・調達するべきサービスの期間・予算・品質・リスク等の相場観や現実感を教えていただき、
・法務としてのコネクションを活用して競争的調達を実施し、
・調達手配完了後、期間、予算、品質、使い勝手が最適化されるよう、外注管理をお願いしたい」
するので、見積もりをお願いしたい 、という要請です。
依頼部門の担当者から、契約書のチェックを要請された場合、まず以上の1ないし6のうちどの要請であるのかを確認すべきです。
問題なのは、依頼部門の担当者自身が、そもそも契約書をまったく読んでおらず、自らの要請の趣旨すらつかめず、ただ意味もわからず
「契約書のチェックを乞う」
と言っている場合です。
この場合、依頼部門の担当者の要請の本質は、1ということになりますので、当該担当者にそのことを自覚させ、今後のことも考え、少なくとも契約書を独力で読む程度のことはさせるべきであり、その上で、依頼の本旨を確認し、所要の対応をすべきです。
なお、このような依頼部門の要請の趣旨を、依頼部門の担当者自身に理解させ、その後の法務部としてのエンゲージスタンスや役割や責任範囲を明確にするため、上記のような要件を明確化したRFPともいうべき、
契約書受審申請書
といったフォームを整備し、運用することが推奨されます。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:
企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所