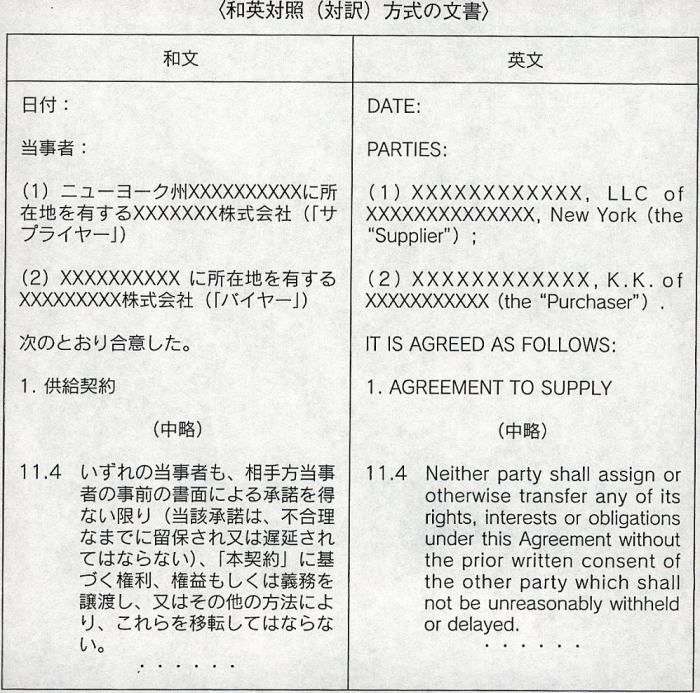海外ビジネス未経験の企業が新しく海外に進出する場合、
「海外ビジネスを初めて展開するが、取引や手続きが不案内で不安この上ないが、他方、自社に海外ビジネス経験者や海外法務ができる者がおらず、支援を求めたい。具体的に何が問題で、これらをどういう手順で、どんな支援を求めて不安解消していくべきか?」
というかなり曖昧で何が不安かすら特定できない漠たるニーズが発生する場合があります。
まず、この不安には、いくつか不安の種別やレベルが観念できるので、こちらから整理してみましょう。
海外ビジネスにおける不安の正体を具体的に分類しますと、
1 コトバが通じるか不安
2 話が通じているか不安(話が理解できない、わからない、法的云々以前に、経済合理性、目的合理性を判断できない)
3 法的トラップがないか不安
の3段階の不安があり、それぞれの不安が、リスクアセスメントという対処課題上の対象事項となります。
1 コトバが通じないことの不安
まず、コトバが通じる通じないの不安は、信頼できる翻訳業者に翻訳を依頼すれば解消できます。
なお、翻訳業者が信頼できなかったり、取引相手が行った翻訳や取引相手が手配した翻訳は、間違いやトラップが仕込まれている可能性があります。
また、国によっては、高い費用にかかわらずいい加減で適当な人間が適当に処理する、ということもあります。
この点、普通の日本人が行う仕事の品質で考えると、大きな失敗をします。
日本人の仕事の品質や出来栄えや費用対効果は、世界でみても突出していて、このことは、翻訳であれ、コンサルティングであれ、法務サービスであれ、事情は変わりません。
信頼できない翻訳については、バックチェックをすることも含め、きっちり不安の根源を解消しておく必要があります。
2 話が通じないことの不安(話が理解できない、わからない、法的云々以前に、経済合理性、目的合理性を判断できない)
きっちりした翻訳文が入手され、和文に修正された内容をみても、例えば、
====================>引用開始
第二十七条の二第二項から第六項まで、第二十七条の三(第一項後段及び第二項第二号を除く。)、第二十七条の四、第二十七条の五(各号列記以外の部分に限る。第五項及び次条第五項において同じ。)、第二十七条の六から第二十七条の九まで(第二十七条の八第六項、第十項及び第十二項を除く。)、第二十七条の十一から第二十七条の十五まで(第二十七条の十一第四項並びに第二十七条の十三第三項及び第四項第一号を除く。)、第二十七条の十七、第二十七条の十八、第二十七条の二十一第一項及び前条(第二項を除く。)の規定は、前項の規定により公開買付けによる買付け等を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定(第二十七条の三第四項及び第二十七条の十一第一項ただし書を除く。)中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、第二十七条の二第六項中「売付け等(売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「売付け等」と、第二十七条の三第二項中「次に」とあるのは「第一号及び第三号に」と、同項第一号中「買付け等の期間(前項後段の規定により公告において明示した内容を含む。)」とあるのは「買付け等の期間」と、同条第三項中「公開買付者、その特別関係者(第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。)その他政令で定める関係者」とあるのは「公開買付者その他政令で定める関係者」と、同条第四項前段中「当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「次の各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付するとともに、当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該公開買付者が発行者である株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者」と、同項各号中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、第二十七条の五ただし書中「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と、第二十七条の六第一項第一号中「買付け等の価格の引下げ(公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者(第二十七条の十第一項に規定する対象者をいう。)が株式の分割その他の政令で定める行為を行つたときは内閣府令で定める基準に従い買付け等の価格の引下げを行うことがある旨の条件を付した場合に行うものを除く。)」とあるのは「買付け等の価格の引下げ」と、同条第二項中「買付条件等の変更の内容(第二十七条の十第三項の規定により買付け等の期間が延長された場合における当該買付け等の期間の延長を除く。)」とあるのは「買付条件等の変更の内容」と、第二十七条の八第二項中「買付条件等の変更(第二十七条の十第三項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)」とあるのは「買付条件等の変更」と、第二十七条の十一第一項ただし書中「公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係る株券等の発行者若しくはその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)の業務若しくは財産に関する重要な変更その他の公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事情(政令で定めるものに限る。)が生じたときは公開買付けの撤回等をすることがある旨の条件を付した場合又は公開買付者に関し破産手続開始の決定その他の政令で定める重要な事情の変更が生じた」とあるのは「当該公開買付けにより当該上場株券等の買付け等を行うことが他の法令に違反することとなる場合又は他の法令に違反することとなるおそれがある事情として政令で定める事情が生じた」と、第二十七条の十三第四項中「次に掲げる条件を付した場合(第二号の条件を付す場合にあつては、当該公開買付けの後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合(第二十七条の二第八項に規定する株券等所有割合をいい、当該公開買付者に同条第一項第一号に規定する特別関係者がある場合にあつては、当該特別関係者の所有に係る株券等の同条第八項に規定する株券等所有割合を加算したものをいう。)が政令で定める割合を下回る場合に限る。)」とあるのは「第二号に掲げる条件を付した場合」と、第二十七条の十四第一項中「、意見表明報告書及び対質問回答報告書(これらの」とあるのは「(その」と、同条第三項中「並びに第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定」とあるのは「の規定」と、同条第五項第一号中「第二十七条の八第三項」とあるのは「第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の八第三項」と、同項第二号中「第二十七条の十第八項若しくは第十二項又は前条第三項」とあるのは「第二十七条の二十二の二第七項」と、第二十七条の十五第一項中「、公開買付報告書、意見表明報告書又は対質問回答報告書」とあるのは「又は公開買付報告書」と、同条第二項中「公開買付者等及び対象者」とあるのは「公開買付者等」と、前条第一項中「若しくは第二十七条の二第一項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者」とあるのは「若しくは第二十七条の二十二の二第一項本文の規定により公開買付けによつて上場株券等の買付け等を行うべきであると認められる者」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第二十七条の二十二の二第二項において準用する第一項」と読み替えるものとする。
<====================引用終了
といった日本語が出てきたら、この言語のカタマリを目にした時に頭の中に投影される認識風景は、

といったものとなり、
「なんだ、これ。日本語で書いてあるが、日本語の文章ではないだろ。暗号か呪文か? まだ般若心経の方が、なんとなくだが意味はわかるが、この不気味で奇っ怪な呪文か暗号は何なんだ・・・・」
という機能的非識字の状況に陥ります。
この場合、機能的非識字の状態に陥っているわけですから、知ったかぶりのままやり過ごしたところで、何日経過しても、何ヶ月経過しても、何年経過しても、不安が払拭されず、却って不安が増殖するだけです。
機能的非識字を解消し、不安をなくすためには、
「日本語の翻訳」「日本語の意味翻訳」「日本語の機能的解釈」
といった作業が必要になります。
これは、法律に長けた経験豊かな法務担当者が必要となります。
このような人材が不在であれば、適切な弁護士に外注して、
「日本語の翻訳」「日本語の意味翻訳」「日本語の機能的解釈」
を支援してもらうべきです。
弁護士というと、後述の
「法的トラップの発見と特定と解消手段の構築」
だけ行うイメージがあります。
しかし、特に、海外法務を支援する企業法務系法律事務所で中堅中小企業やベンチャー企業に理解と配慮のあるところでは、
「法律に長けた経験豊かな法務担当者」
を配備せずに海外ビジネスを始めるという企業に対する
「臨時法務部機能提供サービス」
といった形で、この種の
「日本語の意味翻訳」
を支援することもあります。
ちなみに、この
「日本語の翻訳」「日本語の意味翻訳」「日本語の機能的解釈」
を軽視し、
「不安を解消しないまま、巨額の海外ビジネスを進め、その結果、倒産の危機に瀕する」
という
「歴史に燦然と残る大しくじりをやらかした、日本を代表する大企業」
があります。
電機メーカー東芝は、7125億円もの損失を原子力事業全体で発生させ、2016年4~12月期の最終赤字は4999億円となり、同年12月末時点で自己資本が1912億円のマイナスという、債務超過の状況に陥りました。
この惨事のグラウンド・ゼロ(根源的起点)は、
意思決定者(経営陣)が機能的非識字状態に陥っていたことと、
にもかかわらず、
「日本語の翻訳」「日本語の意味翻訳」「日本語の機能的解釈」
を行うことなく、機能的非識字状態のまま契約に突入した、
というあまりに未熟で愚かで情けない失敗にあります。
東芝傘下のウェスティングハウスは、2015年末に買原発の建設会社、米CB&Iストーン・アンド・ウェブスターを買収した際、買収直後に、ある価格契約を締結しました。
複雑な契約を要約すると、
「工事で生じた追加コストを発注者の電力会社ではなくWH側が負担する」
というものでした。
原発は安全基準が厳しくなり工事日程が長期化し、追加コストは労務費で4200億円、資材費で2000億円になりました。
しかし、問題は担当者以外の経営陣が詳細な契約内容を認識していなかったことにあり(機能的非識字状態)、にもかかわらず契約締結処理を敢行したことにありました。
原子力担当の執行役常務、H(57)らは
「米CB&Iは上場企業だったし、提示された資料を信じるしかなかった」
と悔しさをにじませた、とされます。
「提示された資料を信じるしかなかった」
という弁解ですが、いかにも他に選択肢がなかったという他律的で外罰的な言い訳をしていますが、別に、アタマに銃を突きつけられて契約を點せられたわけではありません。
自らが自らの責任でやらかしたアホなミスであり、自己責任、因果応報、自業自得の帰結であり責任逃れのしようがない、愚かな考えと愚かな行動の結果です。
(以上、出典は、日経新聞2017年2月21日付記事 「もう会社が成り立たない」東芝4度目の危機 (迫真))
提示された資料を信じず、不安に感じ、不安を放置せず、きっちりと理解できるまで、
「日本語の翻訳」「日本語の意味翻訳」「日本語の機能的解釈」
さえきっちり行ってさえいれば、こんな馬鹿げた事件は防げたところです。
にもかかわらず、これを漫然と怠ったことによる、歴然たる人災です。
なお、話を確認する、というプロセスについては、
「ビジネス面での合理性」「ビジネス面での目的合理性や経済合理性」
の検証や確認も含まれます。
こちらは、企業内部において、機能的非識字状態を克服した後、
話の内容の整合性(目的とする取引が文書として表現されているか)や、
話の内容の合理性(1万円札を3万円で購入するような不利でアホな内容となっていないか)
を確認・検証する必要があります。
そもそも、どういう目的でやっているのか、そんなプロセスが必要かどうか、目的とプロセスが整合しているか(=「無残に失敗した日本最大の失敗公共事業」である太平戦争のように、目的不明、プロセスむちゃくちゃ、目的とプロセスが完全矛盾、といった欠陥がないかどうか)については、
「法的チェック以前の段階の話」
です。
もし、この段階で危険や不安やリスクがあるなら、これを解消すべきであり、解消できないのであれば、サンクコストとの兼ね合いも視野に入れて、取引見合わせ、ビジネス撤退も考えるべきです。
いずれにせよ、コトバが通じてない状況を克服した後、話の筋や、目的整合性、ビジネス合理性をを把握し、検証する作業をしっかり行うことが推奨されます。
3 法的トラップがないか不安
最後に、法的トラップの有無についての確認作業に入ります。
これは、おそらく外部の弁護士に依頼して進めていくことが多いと思います。
ただ、弁護士は
「法的」トラップ
は確認できますが、
「ビジネス面での合理性」「ビジネス面での目的合理性や経済合理性」
は判断できません(指摘をしたり、任意の付加サービスとしてお節介を焼いてくれる場合もあるでしょうが、本質的な依頼事項から外れます)。
なお、法的トラップにも、お国柄や記述されざる運用といったものが含まれますので、経験のある弁護士や、経験から保守的考察ができる弁護士等を起用することが推奨されます。
4 全体の段取りや遂行実務の構築
法務担当者は、以上のプロセスの全体の段取りを考え、必要な資源を調達し、効率的に運用するマネジメントが求められます。
因数分解して、相応のスピードと合理性をもって事に当たれば、さほど難しいことではない、と考えられますし、開成高校2年生の平均的な成績の生徒にやらせても、十分できる程度の仕事です。
とはいえ、
「そんな面倒くさいことできないけど、カネがあるので、カネを払って済ませたい」
ということもあり得ます。
こういう場合、法律事務所等で対応人員を用意し、ホットラインを開設し、一次対応から最終対応処理まで一貫して引き受けてもらう、という外注手配による対応もありえます。
その場合のコストは、商社の法務部スタッフの給与をイメージした上で、そのようなスタッフをテンプスタッフとして、緊急に臨時雇用するような条件(緊急かつ臨時に手配することや、手配行為そのものについて、プレミアムが生じる)をイメージすればよいでしょう。
よほど人材難か、よほどカネが有り余っている企業でもない限り、検討にすら値しないオプションですが、法務体制が貧弱な企業にとっては、積極的検討に値する打開策です。
海外進出を試みる企業の中には、
「バカにするんじゃねえ。何が機能的非識字だ。字くらいよめらァ」
「ビジネスのことなどいちいち外の人間に聞かなくてもわかるわい」
「このくらいの契約書読めなくてどうする。オレでもできるわ」
と反発され、噛み付かれるところもありますが、実際、やってみると、
・できない、
・できるが、時間がかかりすぎてどうにも進まない、
・できないし、面倒だし、不安だが、不安は放置して乗り越えて、相手を信じて、楽観的にすすめてしまう(その結果、前記の東芝の悲劇の二の舞、三の舞を演じることになる)
という事態に直面することになったりします。
海外進出は、天下の(?)東芝ですら、大失敗して倒産の危機に見舞われるほど、困難であり、相応の体制整備が必要なものです。
したがって、冷静に自社の体制の状況(貧弱性)をみつめ、外部に支援を求めるか、海外進出自体を見直すことを考えるべきです(東芝も、機能的非識字のまま契約処理するような貧弱な経営陣体制であったのに、無謀にも海外進出したことで、倒産の危機に瀕したが、海外に出なければ倒産の危機に至ることもなかったと思われます)。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:
企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所