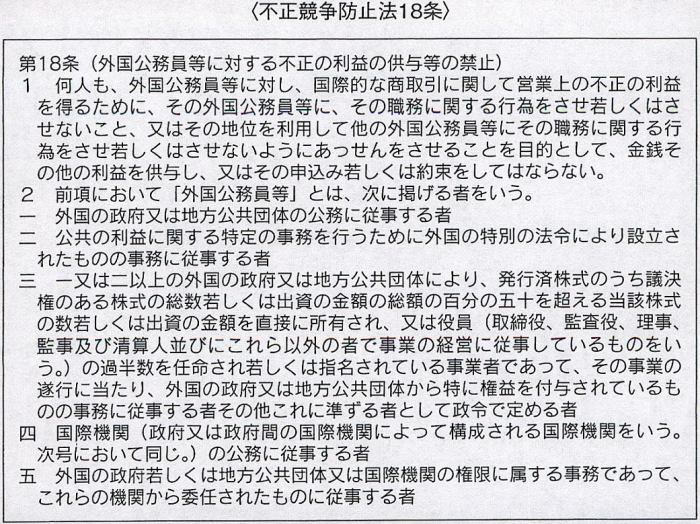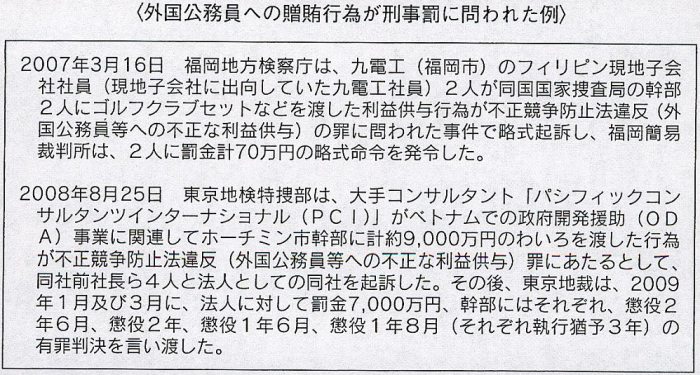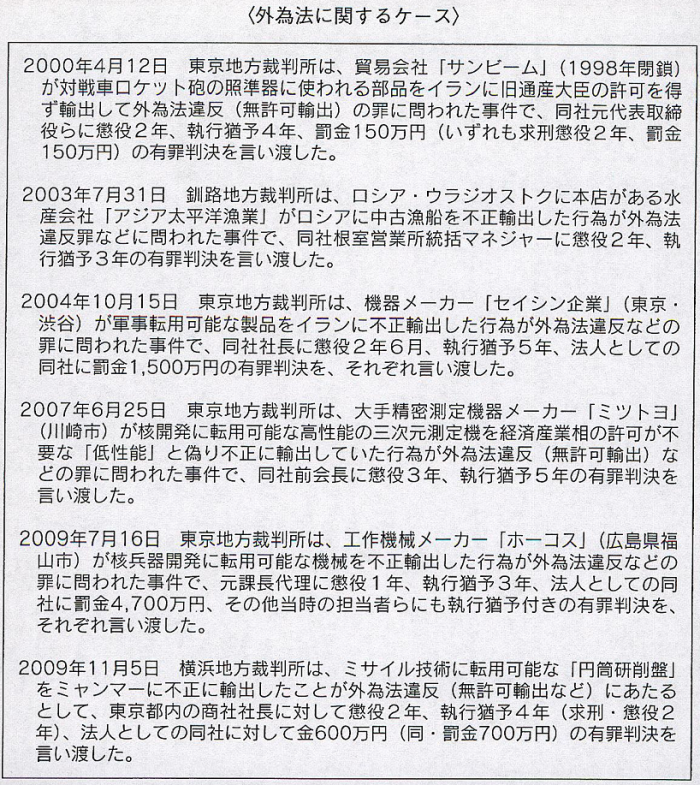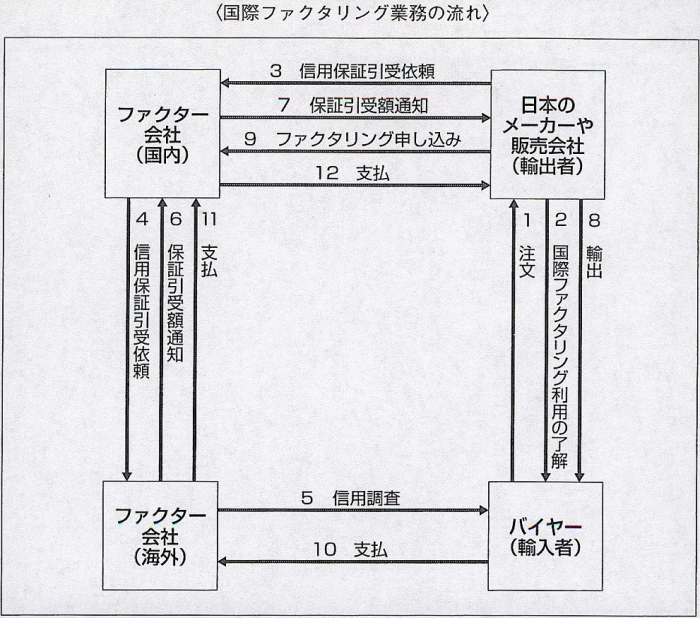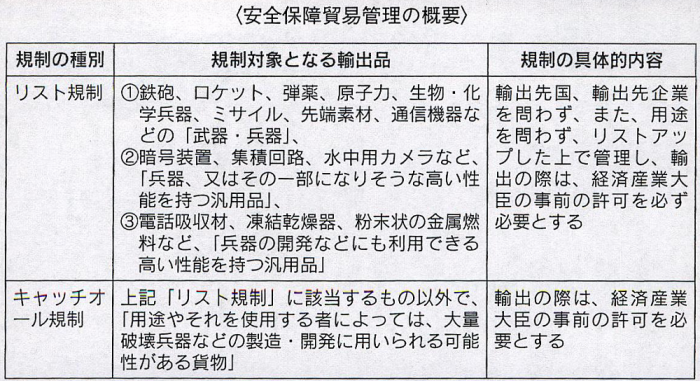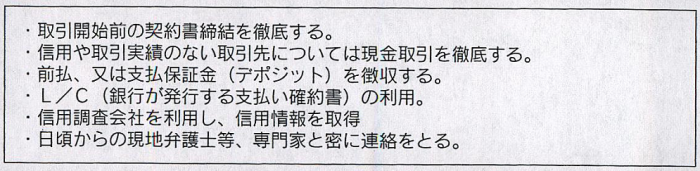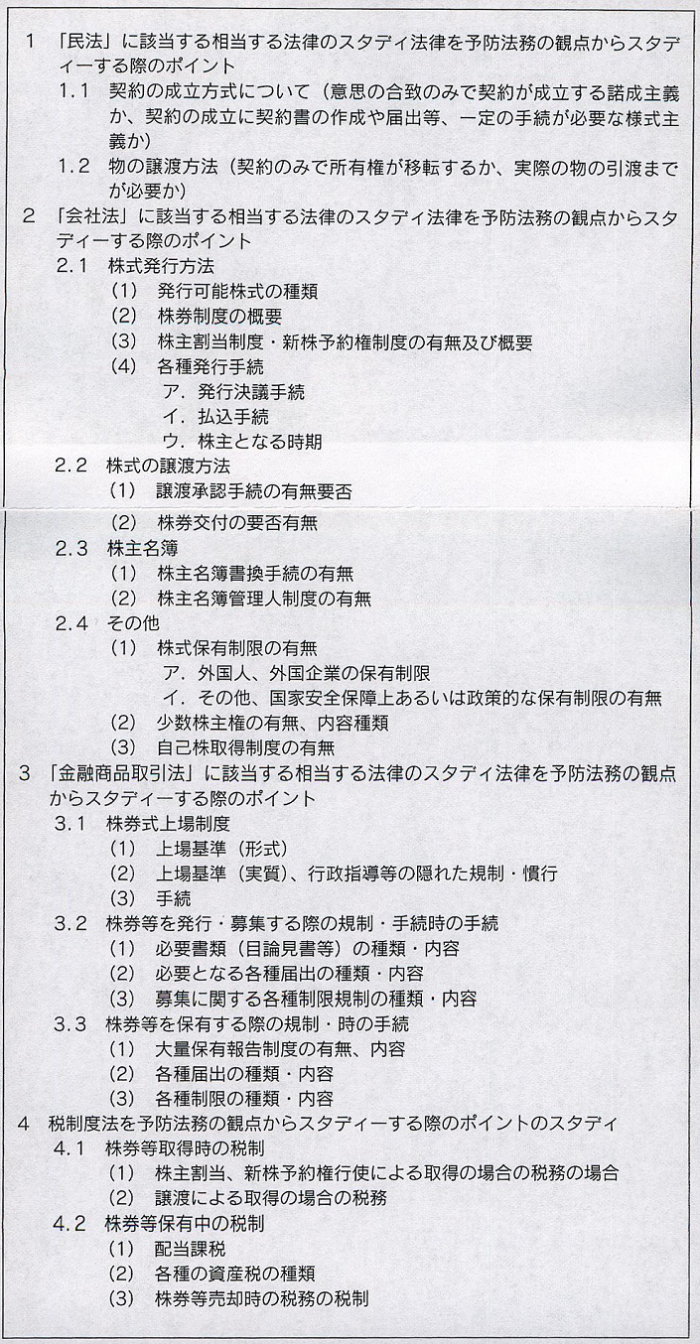非欧米圏の企業や法人と取引する場合、現地の裁判制度が信頼できないケースがあるため、紛争解決手段として、現地裁判所による裁判を忌避し、仲裁手続を活用することが好まれます。
仲裁手続では、自ら仲裁人を選ぶことも可能ですし、仲裁判断は最終的なものとして扱われますし(仲裁においては上訴手続がない)、非公開であることから企業秘密や事件プライバシーを保持することもでき、さらには、海外でも比較的迅速に仲裁判断に基づく強制執行が行えるからです。
ここで、非欧米各国の仲裁手続の状況を概説しておきます。
1 中国
中国の裁判所(人民法院)は自国民保護の偏向傾向があるといわれており、中国企業との間で紛争が生じた場合、外国企業に対し不利な判断を行う危険性があります。
中国もWTO加盟とともに外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(ニューヨーク条約)に加盟することになりましたので、中国の企業・法人と取引する際は、契約上仲裁条項を定めておき、契約紛争が生じた場合には仲裁手続による紛争解決をすることが適切と思われます。
中国国際経済貿易仲裁委員会が北京、上海、深圳等にあり、中国企業と外国企業との間の紛争のほとんどは、これらの地域で仲裁に付されています。
また、中国では、合弁会社の解散は、法律上、中国側の同意が必要とされていますが、仲裁判断をもって解散が認められた場合には、当該法律にかかわらず解散が認められており、ジョイントベンチャー契約において、デッドロック解消手段とともに、仲裁による解決を定めておくメリットは極めて大きいといえます。
2 シンガポール
シンガポールの仲裁機関としては、シンガポール政府機関である貿易発展局と経済開発庁の協力により設立されたシンガポール国際仲裁センターがあります。
旧宗主国であった英国の進んだ弁護士文化があることから、国際取引に豊富な知見を有する有能な仲裁人候補を多数抱えており、スムーズな仲裁が期待できます。
3 香港
香港における仲裁ですが、1985年に設立された非営利の公益法人香港国際仲裁センターが仲裁解決を担っています。
同センターは、アジア地域の国際商事紛争解決の中心となることを日指し、紛争解決インフラの整備に努めるとともに、
「事案誘致」
にも積極的です。
同センターの事案処理実績ですが、2004年の国際仲裁申立件数が280件、2009年では309件、2011年には502件と、その申立件数は確実に増加傾向にあります。
運営管理コード:CLBP692TO694
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:
企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所