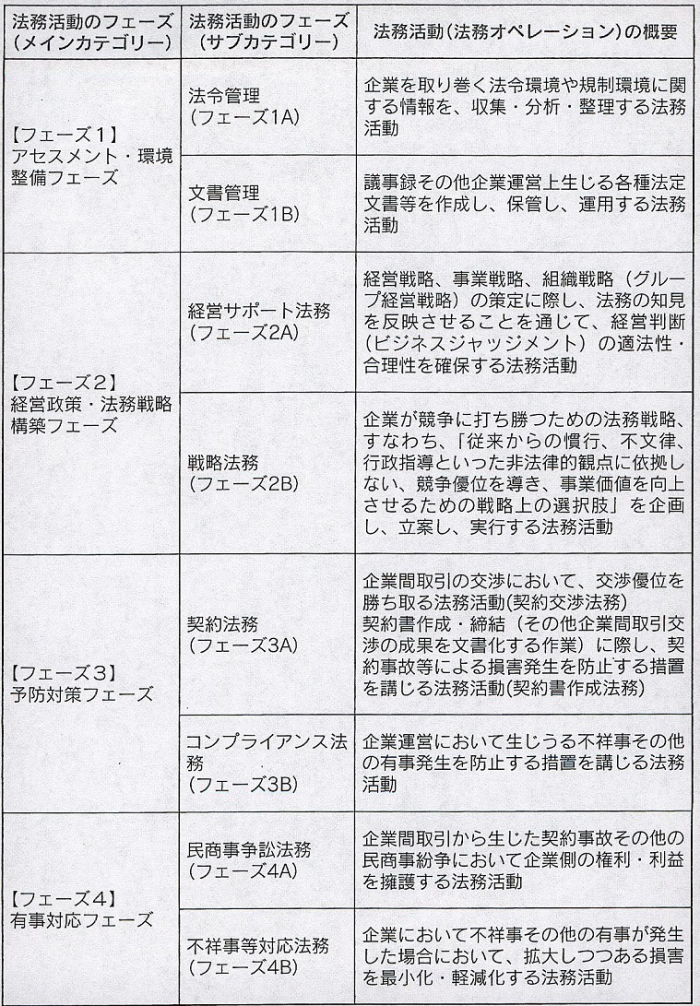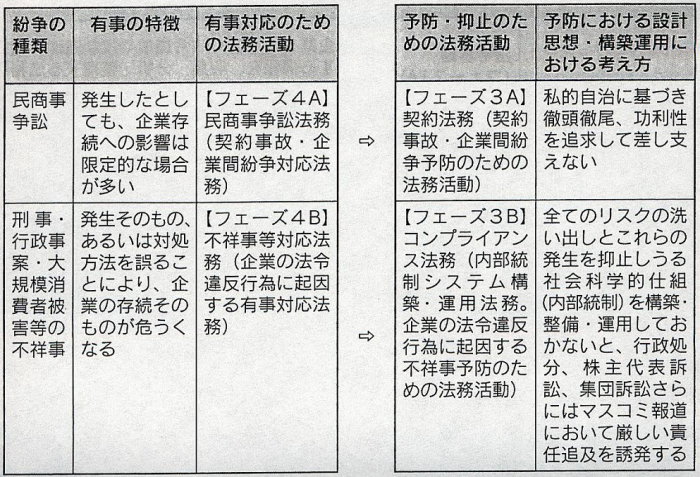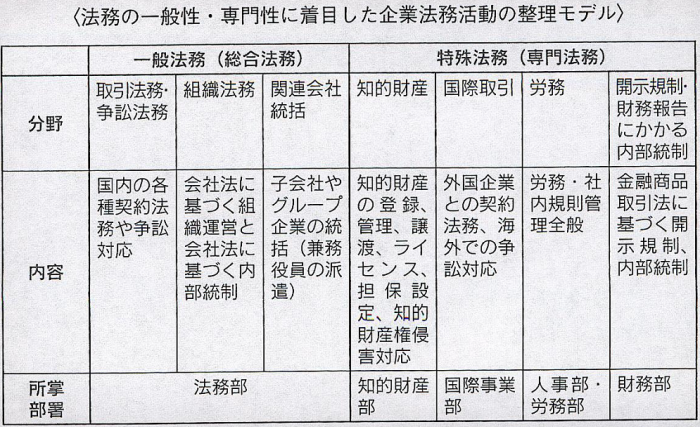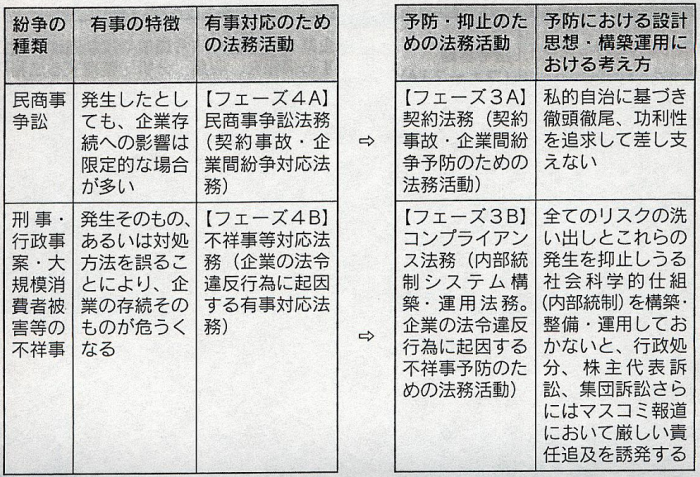満期日が記載された手形であれば、その手形の時効は、記載された満期日から3年後ということになります(手形法70条「満期ノ日ヨリ三年」)。
すなわち、記載された満期日から3年が経過してしまえば、その手形本体が時効にかかってしまいますので、白地補充権が行使できなくなり、手形としての強力な権利行使が不可能となり、単なる民商事債権の証拠としてしか使えなくなります。
他方、満期日が記載されず空白のままである場合については、手形法70条が
「満期ノ日ヨリ三年」
と規定する以上、時効がいつまでたっても始まらないのではないか、との疑問が生じます。
この点については、簡便な金融手段として手形が飛び交い、これに比例して事故が多発した昭和30年代まで裁判例・学説が入り乱れた状態でしたが、昭和36年11月24日に、最高裁が小切手に関する訴訟において、
「『手形に関する行為』(商法501条4号)に準じて5年間の消滅時効にかかる」
との判断を下すことにより、理論上の決着がつきました。
この判例法理により、手形についても、満期が白地とされた場合、振出日から5年間で白地補充権が消滅時効にかかり、以後、手形としての権利行使ができなくなると解釈されています。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:
企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所