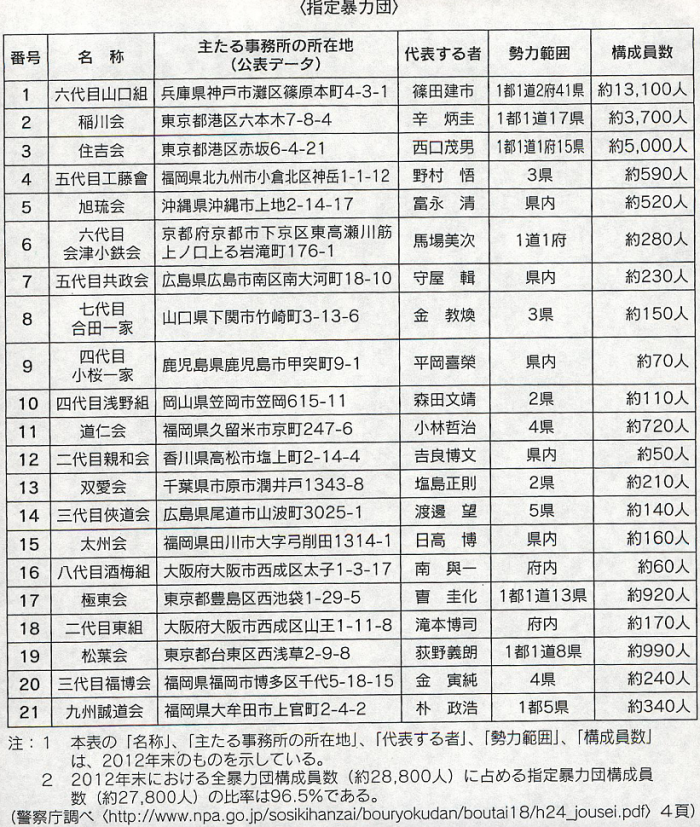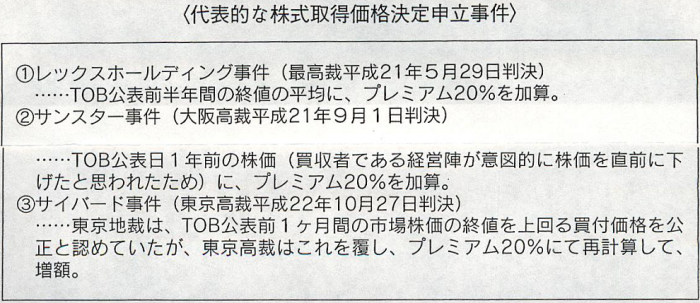買収防衛策とは、
「敵対的買収(敵対的TOB)に対抗する企業(TOBの対象となった企業)が採用する、TOB実現を阻止するための様々な防衛手段の総称」
です。
買収防衛策には、平時の防衛策(予防策)と、実際に敵対的買収を仕掛けられた時の有事の防衛策(対抗策)の2種類があります。
平時における買収防衛策(予防策)が、敵対的買収防衛策の中心となります。
1 株式非公開化
そもそも敵対的TOBは、株式が公開されていて、
「カネさえ出せば、誰でも買える」
という点が前提となって行われるものです。
その意味では、株式公開自体をやめてしまう、すなわち
「非公開化(going private)」
ほど確実な防衛策はありません。
2 安定株主の形成
また、日本企業が古くから行っている方法として、株の持ち合い(相互保有)や従業員持ち株会や親密な取引先による保有等を平時から実施しておくことによって、安定株主を形成し、敵対的買収に備える、というものもあります。
3 黄金株や議決権制限株式の利用
黄金株とは、会社の重要事項の議決を拒否できる権限がある株式(種類株式のうちの拒否権付株式)をいいます。
(経営陣にとって)友好的な会社に対して事前に黄金株を付与しておけば、敵対的TOB等によって普通株式を大量に買い占められたときでも買収者による合併提案を否決することができますので、黄金株は敵対的買収に対する大きな牽制として働きます(ただし、黄金株を発行しながら上場が許されている会社は、国際石油開発帝石株式会社『INPEX』が唯一です。黄金株式の保有者が経済産業大臣であることからすれば、エネルギー政策上の例外と考えられます)。
また、(経営陣が保有する)特定の普通株式以外の株を全て議決権制限株式とする方法なども理論上考えられますが、公開会社においては会社法上の制限(会社法115条)がありますし、上場規則との関係でも困難といえます。
4 チェンジ・ォブ・コントロール条項(チェンジ・イン・コントロール条項)
M&Aを実施するときには、買収対象企業の魅力ある資産(知的財産や有能な人材等)に着目することが多いと思われます。
しかしながら、
「M&Aを実施した後、魅力ある資産が買収対象企業から流出してしまう」
という事態の発生が想定される場合、M&Aを行う意義自体が大きく低下することになります。
このような仕組みを買収対象企業に具備させることは、敵対的M&Aに対する大きな牽制として働くことになります。
そこで、クリティカルな資産について、
「M&A等により支配交替が生じた場合、取引相手に契約を解消するオプションが与えられる」
というような条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)をビルトインしておき、これを敵対的M&Aに対する防衛策として機能させることも可能です。
5 (敵対的買収防衛策としての)資金需要アピール術
また、古典的ながら有効な敵対的買収防衛策として、
「資金需要アピール術」
というものもあります。
6 ライツプラン
現時点において、一般的に用いられている買収防衛策としては、ライツプランと呼ばれるものがあります。
ライツプラン(Rights Plan)とは、敵対的買収者が、対象企業が定める議決権ベースの一定割合(25%と設定される場合が多いようです)を超えた場合、買収者以外の株主に対して、極端に安価な行使価格で対象企業の株式を購入できる新株予約権を発行しておき、敵対的買収者の潜在的持ち株比率を低下させるとともに、安価な株価で株式を追加発行することにより、敵対的買収者の株式価値を低下させるという方法で、
「毒薬(poison pill)」
等と呼ばれることもあります。
ライツプランの種別として、事前警告型と信託型の2種がありますが、信託型はコストが高いという点から一般的ではなく、事前警告型が広く使われています。
敵対的買収者に対する打撃は非常に大きく、株主平等原則に違背するという点で法的な問題も孕んでいる手法といえます。
このことから、
「グリーンメーラー(経営陣に対するゆさぶりをかけて高値買い戻し等不当な要求を行う買収者)や買収対象会社の資産売却などを企図した短期投機目的による買収者等の“濫用的買収者”に対する限定的な対抗措置」
としてのみ、認められます。
“濫用的買収者”か否かを、自己保身を考える経営陣が恣意的な判断で決め付ける危険性があります。
そこで、取締役会とは別の独立の機関を立ち上げ、当該機関によって
「ライツプラン発動のための一定のルール(買収の目的を照会したり、買収後の事業計画の提出を求めるなど)を事前に策定しておき、そうしたルールを守らない敵対的買収者を“濫用的買収者”とみなす」
というフレームワークが採用されます(事前警告型ライツプラン)。
ブルドックソースを巡る敵対的TOB攻防戦(ブルドックソース経営陣対スティール・パートナーズ)においては、最高裁は、ライツプランが相当性を欠く形で発動された場合を除き、株主平等原則に違背しないとし、
(1)スティール・パートナーズ側において、経営支配権取得後の経営方針を明示せず、投下資本の回収方針についても明らかにしない
(2)議決権ベースで約83.4%の株主が賛同している
(3)支配比率は下げられるものの、スティール・パートナーズに対する金銭的補償が行われること
等の点を挙げ、相当性を欠くものではないと判断し、本件でのライツプラン発動を許容しました。
なお、最高裁は、
「スティール・パートナーズに対して一定の金銭補償を行うこと自体、ブルドックソースの企業価値をき損し、株主の共同の利益を害するおそれのあるものということもできないわけではない」
として、上記枠組みが、会社の資金を使って経営陣の保身を行う危険性を指摘しています。
敵対的買収防衛策に関しては、ブルドックソース対スティール・パートナーズ事件で事前警告型ライツプランが裁判所からの一応の“お墨付き”を得た形となりました。
しかし、上記のとおり、同事件では、スティール・パートナーズに対して莫大な額の金銭的補償を支払って追い出した形になっており、裁判所もこのような補償措置を重視して、防衛策を許容したものと考えられます。
今後の敵対的買収防衛策に関しては、ライツプランを前提として、
「買収者側にどの程度の金銭的補償をなせば、防衛策発動が許されるのか」、
いわば“立退料の具体的金額”をめぐって議論が深められていくことになるかと思われます。
ここで、ライツプランの導入状況を見てみると、株式会社レコフの調査によれば、買収防衛策の導入社数は2008年末の569社をピークに漸減傾向で2013年4月時点では514件にとどまり、また、いったん導入したものの中止した会社は累計で123社に上るとのことです。
この意味では、ライツプランの導入企業は減少傾向にあるといえると思われますが、その背景には、金融商品取引法におけるTOB規制が整備されてきたことで、不意打ち的な敵対的TOBが減少していることや、企業の経営権の問題は最終的に株主の判断によるべきとの考えが広がっているのではないかと考えられます(防衛策の廃上がなされた企業においては、安定株主率を高めたりして、「防衛策はもはや不要」との判断に至った可能性もありうるところです)。
運営管理コード:CLBP554TO559
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:
企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所