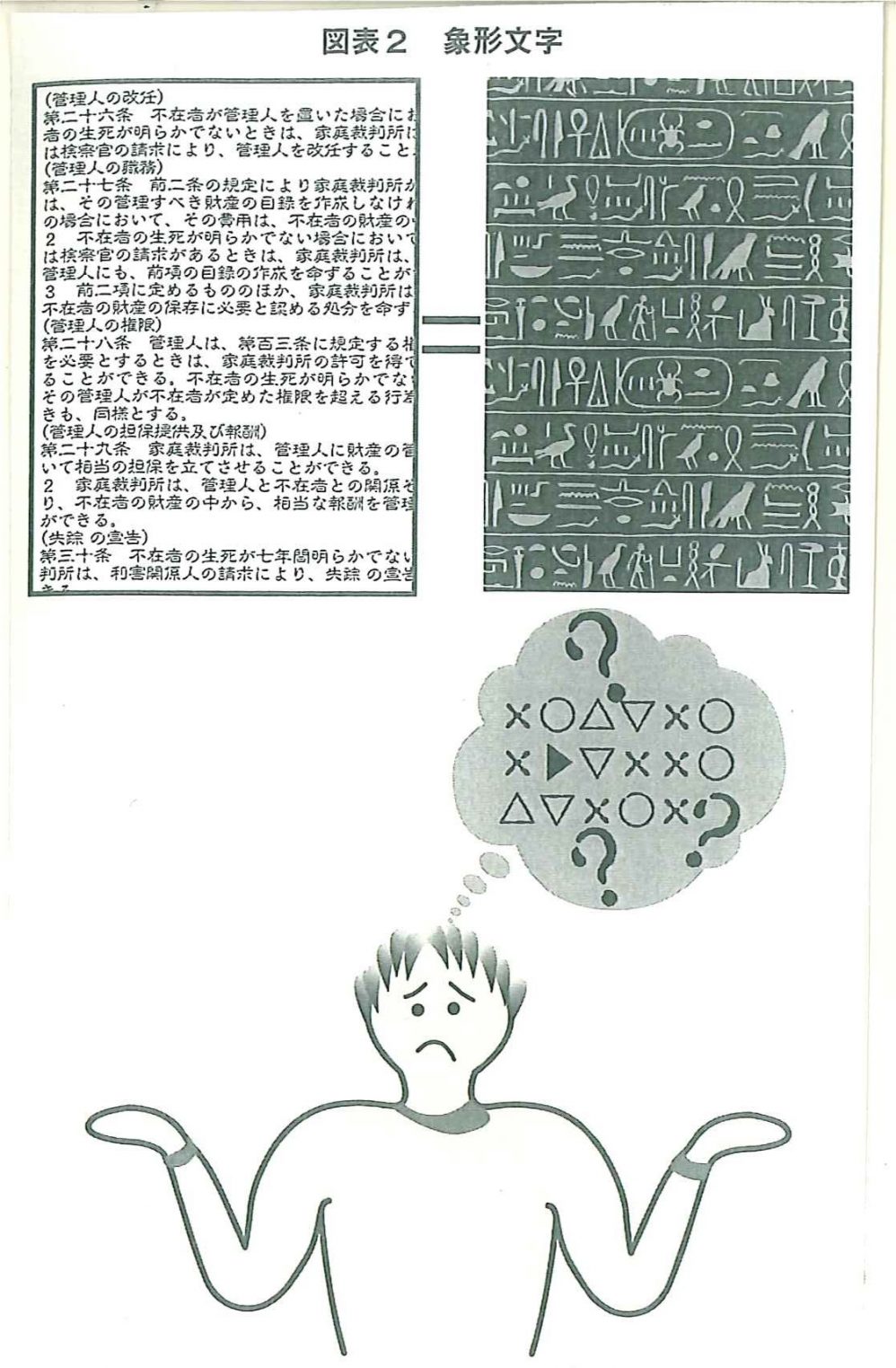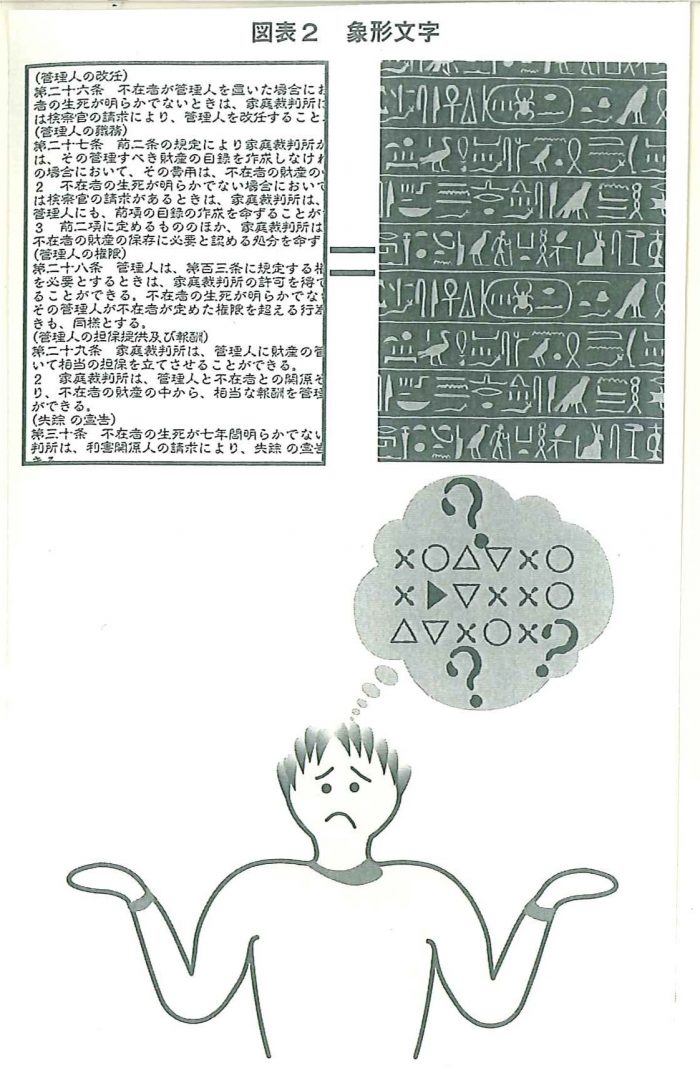字が読めない人のことを文盲といいます。
文明社会においては、学校教育制度が普及し、この文盲は駆逐され、
「字が読めない知能水準の方々」
の存在は一定の文明をもつ社会においては完全に撲滅できた、と考えられてきました。
ところが、我が国を始めとした先進諸国で、新たなタイプの文盲が静かに増えている、という話があるようです。
機能的非識字(機能的文盲)とは、文字自体を読むことは出来ても、文章の意味や内容が理解できない状態、と定義されます。
「言葉はわかっても、話が通じない、特異な知能水準の方々」
という意味なんでしょうが、私は、そんなに珍しいとは思いません。
経験上の認識として、
「言葉はなんとなく通じているが、話は全く通じない(し、気持ちや感受性は全く共有できない)」方々
は、社会には相当はびこっていると思います。
実際、かなり年を取った方でも、知ったかぶり、知っているつもり、で、まったく誤解したまま改善もせず矯正もされず、死ぬまで治らない、という方は結構います。
ところで、この、 機能的非識字(機能的文盲)の増殖ですが、社会問題とされておるようです。
すなわち、
「結果として、機能的非識字者は契約書の理解や、書籍・新聞記事の読解が完全にできておらず、社会や政治への参加に支障をきたしていたり、酷い場合には日常生活にも問題が生じている。さらに、周りの人間のみならず、当の本人すらも見かけの識字能力に問題がないがために、機能的非識字によって支障が出ているということが把握されない(自覚していない)という問題を抱え、識字率の高い先進国であっても一定以上の機能的非識字者が存在することが指摘されている」
という形で、改善すべき社会課題として語られているようです。
しかし、この改善の動きは、努力してどうにかなるものではなく、改善できず、無残なまでの失敗に終わるでしょう。
新聞の購読率が約4割というデータがありますから、マジョリティの方々は、新聞は手にしません。
新聞を手にとっても詳しくは読むこともありません。
せいぜい見るのは見出しくらい。
ほとんどの若者は、テレビすら
「長すぎる」
と忌避し、3分くらいの動画をyoutubeで見るのが限界です。
ある程度の思想や概念を伝える長い文章は、機能的非識字の方々の平均的知能と平均的忍耐力を大幅に超えているようで、ネットで一定の長さの文章を掲載しても、まず読まれることはなく、大多数の方々にとって、ツイッターに収まる程度の文章しか伝わりません。
文章が届けばまだいい方です。
文字や文章すら忌避するインスタグラムやティックトック利用層には、思想内容を文章で伝えることはできず、写真や動画しか受付ません。
ひょっとしたら、世界の文明レベルは、象形文字の時代に退嬰しはじめているのかもしれません。
新聞を読まず、テレビしか観ない子供や平均的日本人に、
「なぜ、新聞を読まない。新聞を読まずにバカになったことは嘆かわしいことだ。新聞を読まなくなったバカな連中が、再び新聞を読めるようになるよう、再教育をすべきだ」
ということを主張する人間がいたとしたら、当該主張者の方が明らかに間違っています。
「どんな知的水準であれ、それなりに社会生活が営める」
「識字や知能に問題がある方でも抹殺されることなく、普通に生かされる」
ということこそが、社会の進歩であり、文明化ですから。
昔は、社会が貧しかったので、字が読めない人間は、社会で生きていくことはできませんでした。
字が読めない、文書が読めない、文書が書けない人間が、そのまま社会に出たら、パワハラにあって、罵声を浴びせられ、矯正されました。
一昔前の日本は、そんな、余裕のない、遅れた、未開で野蛮な社会だったのです。
ところが、現代は、人手不足ということもありますが、社会が進んだおかげで、機能的非識字であれ、社会で普通に暮らせるようになりました。
会社で、新入社員が、
「文章が読めない」
「文章が書けない」
からといって、その程度のことでガミガミ怒り出す、狭量で人権感覚がない人間は、逆に、パワハラ上司として会社や社会から排除されます。
社会に機能的文盲がはびこったら、機能的文盲を減らすより、機能的文盲に併せて社会システムを変えるべきです。
ポリシーと現実がぶつかったらどうするか?
「ポリシーをもって現実を変える」
のは、知能未熟なバカのやることです。
知的な大人は、
「現実に併せて、ポリシーの方を変える」
ということで課題解決します。
いったん増えたバカは減りません。
マジョリティになった機能的文盲はパワーを持っています。
「1人の馬鹿は、1人の馬鹿である。2人の馬鹿は、2人の馬鹿である。1万人の馬鹿は、“歴史的な 力”である。」
これは、日本一の毒舌女性インテリ、塩野七生が『サイレント・マイノリティ』(新潮社、1993年 、163頁)で引用していた一文ですが、
「馬鹿を馬鹿にする恐ろしさ」
と
「増殖してしまった馬鹿に対する、安全保障上の対処哲学」
が凝縮されています。
「小賢しい正しさ」
は、
「数の結束とパワーをもち、増殖を続ける機能的文盲」
の大きな声には、決して敵いません。
「社会において増殖し、一定の数にいたり、もはやパワーをもった機能的文盲」
を改善や矯正しようとしたり、駆逐しようとする努力は、無駄に終わるでしょう。
フェイルセーフ、ホニャララカメラ、漫画やアニメ、交通標識、ピクトグラム。
日本では、
「増殖し、マジョリティとなった機能的文盲」
と向き合ったり、矯正したりしようとせず、
「知能水準は期待できないし、我慢もしない」
ことを前提として、そんな方々でも、容易に理解し、簡単に扱える様々なツールやシステムを開発してきました。
現段階では、機能的文盲が増えつつある、という程度の話ですが、
「新聞からテレビへ、テレビからyoutubeへ」
「ネット記事からツイッターへ、ツイッターからインスタグラムやティックトックへ」
という
「文字によるコミュニケーション文化の後退」
のトレンドをみる限り、機能的文盲どころか、そのうち、ホンモノの文盲も増殖しはじめ、文盲がマジョリティとなり、存在感とパワーを持ち始める日が来るかもしれません。
機能的文盲が増えたなら、機能的文盲を改善・駆逐するより、
「機能的文盲のレベルに合わせた、咀嚼に咀嚼を重ね、字が嫌いで、我慢も嫌いなマジョリティでも、一瞬で判るような話の仕方」
をすべきであり、そのような咀嚼が困難な難しい話を機能的文盲の方にすること自体、控えるべきです。
機能的文盲のみならず、さらにホンモノの文盲が増えたなら、字を使わず、写真や動画や象形文字を使って、思想内容を伝えるべきです。
それが、正しい社会のあり方です。
ところで、社会全般がこのように機能的文盲者が増殖し、世界の文明レベルが、象形文字の時代に退嬰しはじめているな状況ですが、ビジネス現場においても、特に法律文書に関しては、
「機能的文盲」
すなわち
「文字自体を読むことは出来ても、文章の意味や内容が理解できない状態」
に陥っているビジネスパースンは相当多くの割合で存在しているものと推定されます。
そんなことが、実際あるのでしょうか?
実は、つい最近、この法律文書の機能的識字障害が原因となって、日本を代表する大企業が倒産の危機に陥った事件が起こりました。
電機メーカー東芝は、7125億円もの損失を原子力事業全体で発生させ、2016年4~12月期の最終赤字は4999億円となり、同年12月末時点で自己資本が1912億円のマイナスという、債務超過の状況に陥りました。
この事件の背景として、こんなやりとりがあったそうです。
(引用開始)
会長の志賀が
「WHで数千億円の損失が発生するかもしれません」
と報告すると出席者は声を失ったという。ようやく
「もう減損したはずでは」
との問いが出ると
「別件です」。
社長の綱川は
「何のことなのか理解できない」
と繰り返した。
WHが15年末に買収した原発の建設会社、米CB&Iストーン・アンド・ウェブスター(S&W)でただならぬ出来事が起きた。
105億円のマイナスと見ていた企業価値は6253億円のマイナスと60倍に膨らんでいた。「買収直後に結んだ価格契約が原因」
と、ある幹部は打ち明ける。
複雑な契約を要約すると、工事で生じた追加コストを発注者の電力会社ではなくWH側が負担するというものだ。
原発は安全基準が厳しくなり工事日程が長期化した。
追加コストは労務費で4200億円、資材費で2000億円になった。
問題は担当者以外の経営陣が詳細な契約内容を認識していなかったことにある。
米CB&Iは上場企業で、原子力担当の執行役常務、H(57)らは
「提示された資料を信じるしかなかった」
と悔しさをにじませるが、会計不祥事で内部管理の刷新を進めるさなかの失態に社内外から批判の声がわき上がった。
(以上、引用。出典は、日経新聞2017年2月21日付記事 「もう会社が成り立たない」東芝4度目の危機 (迫真) )
この事件のグラウンド・ゼロ(爆心地、根源的発生原因)は、上記の
問題は担当者以外の経営陣が詳細な契約内容を認識していなかったことにある。
米CB&Iは上場企業で、原子力担当の執行役常務、H(57)らは
「提示された資料を信じるしかなかった」
と悔しさをにじませる
という経緯にあります。
簡潔にいえば、
「当該プロジェクトの責任者であったH氏が、契約書は読んでいたものの、機能的識字レベルに問題があり、その内容を理解していなかった」
ことにある、
さらにいえば、
「言葉や字面はなんとなく理解していような気になっていたが、話の中身は全く理解しておらず、数千億円もの損失を発生させうるメカニズムを内包した取引の契約であったにもかかわらず、そのリスクを認知しない状態で、適当かつ杜撰に取引を進めた」
という、愚劣で痛々しい失敗が原因で、東芝に7000億円超の損失を発生させ、内部留保を吹き飛ばし、債務超過に陥らせた、
という話です。
これは、ビジネスパースンの法律文書に対する機能的識字レベル(機能的文盲状態)をよく表しているエピソードです。
当時の日本を代表する大企業、天下の東芝のトップマネジメントですら、この状態です。
経験上の蓋然性に基づく合理的推測を働かせれば、 他の企業一般の、マネジメントレベルを含む、ビジネスパースン一般の法律文書に対する機能的識字レベルがどの程度かは想像がつきます。
おそらく、一般のビジネスパースンが訴状や内容証明等の通知書や契約書や約款等の法律文書を目にした場合、意味内容の把握という点において、
「どこか遠くの国の、あるいは古い時代の、知らない部族が、象形文字で刻んだ呪いの言葉の羅列」
程度にしか理解できていないものと推定されます。
他方で、重要な経営判断を下すべき立場にある者について、企業の生死を決する重要な取引にまつわる契約文書を、
「『どこか遠くの国の、あるいは古い時代の、知らない部族が、象形文字で刻んだ呪いの文字の羅列』程度にしか理解できていない認知状態」
で、
詳細な契約内容を認識せず、
「提示された資料を信じるしかなかった」
として適当かつ杜撰に調印処理してしまえば、第2、第3の東芝の悲劇が発生します。
このような状況を踏まえて、責任あるビジネスマンの方については、
・「機能的文盲にならないよう、しっかりと知的鍛錬を継続する」
か、
・「自らは、機能的文盲であり、かつ、これを改善するための知的鍛錬を行う時間も余裕もなく、機能的文盲者として生きていく自覚と覚悟をもちつつ、機能的文盲でない十分な知性とスキルを有する側近ないし参謀を近侍させ、この者から読解支援等のサービスを常時受けるようにすべき(そのための時間と費用と手間をきっちりと考えた執務体制を構築すべき)」
のいずれかまたは双方を充足すべきです。
実際、前者、
「機能的文盲にならないよう、しっかりと知的鍛錬を継続する」
については、かなりの時間と費用と労力を犠牲にする覚悟が要りますし、ビジネスマンの多忙さを考えれば、持続可能性を期待できません。
結局、
トップマネジメントやプロジェクトマネージャーの側近ないし参謀として近侍する企業法務担当者や顧問弁護士が、
・一般ビジネスパースンの(法律文書に対する)機能的識字レベルの壊滅的な低劣さを、(善し悪しや改善の必要性は別として)現実として、しっかりと受け止め、理解し、
・その上で、「法律文書については、しっかりとした機能的識字支援(文盲介護)が、重要な価値を有するサービスである」という認識の下、
・(もともと重篤な機能的文盲状態に陥っているビジネスパースンが)確実な理解に至るまで、咀嚼に咀嚼を重ねて、会話の水準を下げるなど、内容を伝える努力を行う
ということが絶対的必要となる、ということが結論づけられます。
前述の、東芝の悲劇も、
・プロジェクトの責任者であったH氏をはじめとしたトップマネジメントの(法律文書に対する)機能的識字レベルの壊滅的な低劣さを、(善し悪しや改善の必要性は別として)現実として、しっかりと受け止め、理解し、
・法律文書については、しっかりとした機能的識字支援(文盲介護)が、重要な価値を有するサービスである、という認識の下、
・ (もともと重篤な機能的文盲状態に陥っているビジネスパースンが)確実な理解に至るまで、咀嚼に咀嚼を重ねて、会話の水準を下げるなど、内容を伝える努力を行っていれば、
問題は担当者以外の経営陣が詳細な契約内容を認識していなかったことにある。
米CB&Iは上場企業で、原子力担当の執行役常務、H(57)らは
「提示された資料を信じるしかなかった」
と悔しさをにじませる
といった愚劣で無残で言い訳ができない失敗に至ることはなく、また、東芝が7000億円超もの損失を被り、また、債務超過に至ることもなかったであろう、と思います。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:
企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所